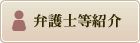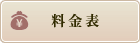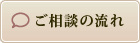独占禁止法違反(不当な取引制限の罪、カルテル)について
不当な取引制限の罪とは何か
独占禁止法第89条1項1号後段は以下のように規定しています。
1.第3条の規定に違反して・・・不当な取引制限をした者」
では、「不当な取引制限」とはどのような行為をさすのでしょうか。
独占禁止法第2条6項を見てみます。
 不当な取引制限として代表的なのは、カルテルや入札談合といった行為です。
不当な取引制限として代表的なのは、カルテルや入札談合といった行為です。
 カルテルとは
カルテルとは事業者が連絡を取り合い、本来、各事業者が各自で判断して決めるべき商品の価格や販売量、生産量などを共同して決定する行為のことをいいます。
 入札談合とは
入札談合とは国や地方公共団体などが行う公共工事や物品調達に関する入札において、予め受注する業者や入札金額などを決めてしまう行為のことをいいます。
不当な取引制限の罪に当たる要件としては、以下が挙げられます。
- ① 他の事業者と共同したこと
- ② 事業活動を相互拘束したこと
- ③ 公共の利益に反したこと
- ④ 一定の取引分野における競争を実質的に制限したこと
- ⑤ 公正取引委員会の告発(独占禁止法96条1項)
以下では、これらのうち①・②・④の要件がどのような場合に認められるのかをみていきましょう。
①他の事業者と共同したこと
「共同した」といえるためには、行為が外形的に一致しているだけではなく、「意思の連絡」があることが必要であると考えられています。
なぜならば、行為が外形的に一致しているだけであれば、事業者が各々で価格等の決定を行った結果である可能性も残るからです。
それではどのような場合に「意思の連絡」があると考えられるかについてですが、明示的な協定等が存在する場合だけではなく、黙示的な示し合わせ等があれば足りると考えられています。
事業者が他の事業者と情報交換をした結果、同じような価格帯に引き上げを行ったような場合には、他の事業者の行動と無関係な判断であるということを示す特段の事情がなければ、意思の連絡があると推認されてもやむを得ないという判断がされているのです(東京高等裁判所平成7年9月25日)。
そのため、価格の引き上げが同時に行われた場合に「意思の連絡」がないことを争うためにはそれなりの根拠が必要と考えておくべきでしょう。
②事業活動を相互拘束したこと
この要件を満たすためには、競争関係にある事業者が、相互にその事業活動を拘束し、制限が各事業者に共通することが必要とされています(東京高等裁判所昭和28年3月9日)。
その具体的内容においては、事実上の拘束で足りると考えられていますので、法的な拘束力や違約条項がない、いわゆる紳士協定的なものでも要件を満たすと考えられています。
そのため、比較的緩やかに要件を満たし得ると考えておくべきでしょう。
④一定の取引分野の競争を実質的に制限すること
「競争を実質的に制限」されている状態とは、競争自体が減少して、特定の事業者又は集団が、その意思である程度自由に価格・品質・数量その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる形態が現れているか、又は少なくとも現れようとする程度に至っている状態のことをいいます(東京高等裁判所昭和2年9月19日)。
弁護方針
 不当な取引制限の罪を認める場合、その違法な行為をやめた上で、可能な限り早期に、公正取引委員会に自らの違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を単独で行うこと、を薦めています。
不当な取引制限の罪を認める場合、その違法な行為をやめた上で、可能な限り早期に、公正取引委員会に自らの違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を単独で行うこと、を薦めています。
不当な取引制限をした場合、独占禁止法第7条の2第1項によって、課徴金納付命令が出されることになるのが原則なのですが、上記の対応を取ることによって、場合によっては、課徴金の納付義務が免除されるのです。
すなわち、独占禁止法第第7条の2第10項に以下のように規定されています。
「公正取引委員会は、第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
- 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以降に行われた場合を除く。)であること。
- 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以降において、当該違反行為をしていた者でないこと。」
また、刑事罰との関係でも、上記対応を取ることは大きな意味があります。
すなわち、先述のとおり、不当な取引制限の罪の成立要件の一つに、「公正取引委員会の告発」があるのですが、事実の報告・資料の提出という対応をとった場合、公正取引委員会は告発を行わないという運用をとっているのです。
会社を守るためにも、経営者ご自身の生活を守るためにも、公正取引委員会への報告・協力はとても重要なのです。
また、公正取引委員会の調査開始後であっても、上記対応を取る必要があります。
 告発を回避できる可能性がありますし、刑罰も軽くなることでしょう。
告発を回避できる可能性がありますし、刑罰も軽くなることでしょう。
専門的かつ複雑な問題であり、費やすことになる時間も膨大なものです。
経営者自ら公正取引委員会とのやり取りを行うことは、困難ですし会社にとって悪影響ですから、企業法務、刑事事件に注力する弁護士を窓口とすることが望ましいといえるでしょう。
当事務所には、企業法務チーム・刑事事件チームがあります。チーム間で連携を取って対応にあたることが可能です。まずはお気軽にご連絡ください。
企業犯罪についてはこちら
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか