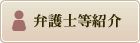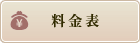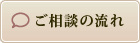死亡事故の加害者はどうなる?処罰や対応すべきこと

死亡事故の加害者は、民事責任、刑事責任、行政上の責任といった複数の責任を負うことになります。
死亡事故は人の死という最悪の結果を招いたものであり、交通事故の中でも最も重大なものといえます。
そのため、以上の責任はいずれも非常に厳しいものとなる可能性があるといえます。
ただし、死亡事故の加害者であっても、事故後に適切な対応をすることにより、法的な責任をできるだけ小さいものに抑えつつ、更生を図っていくことも不可能ではありません。
この記事では、死亡事故の加害者について、加害者が負う責任の内容や、事故後の流れ、事故後において加害者がとるべき対応などを、弁護士が解説します。
死亡事故の加害者の責任や対応について詳しくお知りになりたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
交通死亡事故の加害者とは?
交通死亡事故では、相手を死亡させた側が加害者となります。
一般的な交通事故では、双方ともに過失がある場合は、お互いが相手に対して「加害者でもあり、かつ被害者でもある」というケースになることも考えられます。
ただし、一方のみが死亡する交通事故においては、事故の原因がほとんど被害者側にあるような場合を除いて、生存した側を加害者と考えることになります。
次にご紹介するとおり、死亡事故の加害者となると、法的には3種類の責任が発生することになります。
交通死亡事故の加害者が負う3つの責任とは?
死亡事故の加害者には法律上、民事責任、刑事責任、行政上の責任という3種類の責任が発生することになります。
これらの責任自体は、死者のいない通常の交通事故でも発生し得るものですが、死亡事故の場合には、特に厳しい内容となることが予想されます。
それぞれの責任の内容は、次のとおりです。
刑事責任
死亡事故は刑事罰の対象であり、交通犯罪という犯罪の一種となります。
つまり死亡事故を起こすと、刑事責任が発生するということです。
ただし、死亡事故といってもケースはさまざまであり、事故の態様や原因によって成立する罪名や科される罰則が異なってきます。
交通死亡事故の加害者に成立する可能性があるのは、主に自動車運転死傷行為処罰法違反です(正式名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)。
自動車運転死傷行為処罰法の中でも、死亡事故について成立する可能性のある犯罪にはいくつかの種類が存在します。
成立するための条件や罰則もそれぞれに異なりますので、以下でご紹介します。
危険運転致死罪
法が定める一定の危険な運転によって被害者を死亡させると、危険運転致死罪となります(自動車運転死傷行為処罰法2条)。
ここでのポイントは、「法が定める一定の危険な運転」というところです。
危険な運転での死亡事故がすべて危険運転致死罪になるわけではなく、法が規定している危険運転に該当する場合に限って、危険運転致死罪が成立することになります。
法の定める「危険な運転」とは、以下の8種類です。
- ① アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転
- ② 制御困難な高速度での運転
- ③ 進行を制御する技能を有しないでの運転
- ④ 人や車の通行を妨害する目的で、危険な速度での割り込みや接近する行為
- ⑤ 車の通行を妨害する目的で、走行中の車に接近し又は前方で停止する行為
- ⑥ 高速道路で5の行為を行って走行中の車を停止又は徐行させる行為
- ⑦ 危険な速度で赤信号を殊更に無視する行為
- ⑧ 危険な速度で通行禁止の道路を通行する行為
参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口
これらの行為は、いずれも死亡事故を引き起こす可能性がある危険なものであり、その悪質性は非常に高いです。
このような悪質性の高い運転で死亡事故を起こすことは、特に強く非難されるべきものであり、通常の交通事故と同列に語ることはできません。
実際、悪質な飲酒運転やあおり運転によって被害者が死亡するという悲劇が繰り返され、厳罰化を求める声が後を絶たないという時代背景もあります。
このような流れの中で、一般的な過失運転致死罪と区別して、特に悪質性の高い危険な運転による死亡事故を、危険運転致死罪として処罰するものとされているのです。
準危険運転致死罪
準危険運転致死罪は、アルコールや薬物、又は一定の病気等の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、被害者を死亡させる罪です(同法3条)。
これだけを見ると、さきほどの危険運転致死罪と同じように見えるかもしれませんが、準危険運転致死罪では、正常な運転に支障が生じる「おそれがある」とされている点がポイントとなります。
危険運転致死罪が成立するためには、運転者が正常な運転が困難な状態にあることを認識している必要があります。
運転者が正常な運転が困難であると認識していたことの立証は難しい面があり、危険運転致死罪で立件される件数は多くはありません。
これに対し、準危険運転致死罪ではそのような状態に陥る「おそれ」を認識していれば足りることから、危険運転致死罪での立件が困難なケースをカバーするような意味合いがあるといえます。
また、準危険運転致死罪では、アルコールや薬物だけでなく、統合失調症やてんかんのような特定の病気を原因である場合も含まれます。
準危険運転致死罪の原因となり得る病気は、次のとおりです。
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 低血糖症
- そう鬱病
- 睡眠障害
引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条|電子政府の総合窓口
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、アルコール又は薬物の影響下にある者が過失運転致死罪を犯した場合に、その発覚を免れるために、追加でアルコール等を摂取したり、現場を離れて体内の濃度を減少させたりすることによって成立します(同法4条)。
これは、事故後にアルコールを摂取することによって事故当時に飲酒していたことの立証を不可能にしようとした事案が生じたことから、そのような隠ぺい行為自体を犯罪行為として処罰対象とするものです。
過失運転致死罪
自動車を運転する上で必要な注意を怠り、よって人を死亡させた場合、過失運転致死罪となります(同法5条)。
過失の程度としては、著しい不注意で強く非難すべきものから、軽度の過失まで幅広く含まれますが、どうやっても事故を回避することは不可能だったというような全くの無過失の場合を除き、死亡事故を起こすと原則として過失運転致死罪が成立します。
注意を怠ったと認定され得る例としては、居眠り運転や、わき見運転、前方不注視、信号無視などが考えられます。
過失運転致死傷罪についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。
| 罪名 | 事故の原因 | 罰則 |
|---|---|---|
| 危険運転致死罪 | 飲酒運転、無謀運転など | 1年以上の有期懲役 |
| 準危険運転致死罪 | 飲酒・薬物・病気などの影響下での運転 | 15年以下の懲役 |
| 過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪 | 飲酒・薬物の影響下での運転 | 12年以下の懲役 |
| 過失運転致死罪 | 不注意 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
交通事故の世界では、特に悪質で危険性の高い運転として、無免許運転、飲酒運転、悪質な速度超過の3種を、伝統的に「交通三悪」と呼んで問題視してきました。
飲酒運転や無謀運転による死亡事故は、危険運転致死罪が成立する可能性があることはもとより、仮に過失運転致死罪にとどまる場合であっても、特に悪質性が高いとして重く処罰されることが考えられます。
実際の裁判においても、厳しい判決となった理由として交通三悪に該当することを指摘するものが見られます。
また、近年ではこれらに加えて、あおり運転や運転中のスマートフォン等の使用などについても、三悪に準ずるものとして厳しい目が向けられるようになっています。
「車は走る凶器」という言い回しがありますが、取り扱いを一歩間違えると簡単に人命を奪うことになり得る点で、「凶器」というのは決して大げさな表現とはいえません。
車は日常的に利用するものなので「慣れ」が生じやすいかもしれませんが、それだけ危険なものを扱っているという認識を、いつも心にとどめておく必要があるといえます。
②民事責任
民事責任とは、こちらの過失によって相手に与えた損害を賠償する責任のことを指します。
死亡事故で発生する民事責任としては、精神的な苦痛に対する「慰謝料」や、財産上の損害を償う「損害賠償」などが中心となります。
慰謝料などの賠償金
死亡事故によって被害者は精神的な苦痛を被っており、これを金銭によって賠償するのが慰謝料です。
死亡事故の遺族は、事故によって家族の命をうばわれており、当然ながら強い精神的苦痛を被っています。
そこで、このような精神的な苦痛を金銭によって償わせるために、慰謝料を請求することができます。
また、事故で亡くなった直接の被害者自身も、慰謝料請求権を取得します。
被害者は苦痛を感じる間もなく即死であるという事案も多いかもしれませんが、怪我にとどまる場合は慰謝料を請求できるのに、それより重い結果である死亡の場合には慰謝料を請求できないとしたのでは、バランスを欠いてしまいます。
そこで、即死の事案でたとえ本人に苦痛を自覚する間がなかったとしても、もっと生きたかったという「無念」の感情がきっとあるはずだという発想により、被害者本人にも慰謝料請求権が認められるのです。
もっとも、被害者本人は死亡しており、慰謝料請求権を行使できないことから、遺族がこの権利を相続して加害者に請求することになります。
慰謝料の金額は、被害者の立場によって変わってくるため一律ではありませんが、おおむね2,000万円から2,800万円程度が相場と考えられています。
死亡事故における慰謝料についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。
慰謝料以外の損害賠償
慰謝料は、交通事故加害者が負う賠償項目の一つに過ぎません。
交通事故では、車両などに物的損害が発生していれば、加害者はこれを賠償する義務を負います。
さらに、死亡事故の場合は、被害者が死亡しなければその後の人生で得たであろう利益、典型的には給料相当額についても、財産上の損害として賠償する必要があります。
このような利益は、事故のために獲得する機会を逸した利益という意味で、「逸失利益」と呼ばれます。
逸失利益は、「この程度は稼げたはずだ」という仮定ですので、被害者の年齢や職業などに基づいて計算することになります。
このため、逸失利益の金額は、被害者がどのような属性であったかによって変動してきます。
もし被害者が若ければ、その後の人生での稼働期間も長くなりますので、逸失利益は数千万円や1億円を超える額となることもあり得ます。
死亡事故における逸失利益についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。
行政上の責任
死亡事故では、以上の刑事責任及び民事責任に加えて、さらに行政上の責任も発生します。
交通事故における行政上の責任としては、運転免許の効力の停止や取り消しなどの処分を受ける責任があります。
運転免許ではいわゆる「点数制度」が採用されており、交通違反による点数が一定の基準を超えると、ペナルティが科されます。
死亡事故を起こした場合は、過失運転致死罪でも15点以上の点数が加算され、これだけで免許取り消しの基準に達します。
さらに、より重い危険運転致死罪が成立するケースでは、62点もの点数が加算され、欠格期間も5年間と長期に及びます。
交通死亡事故では、加害者には法律上、刑事責任、民事責任、行政上の責任という3つの責任が発生しますが、法的なものとは別に、社会的な責任が発生することもあります。
たとえば、加害者が公務員であれば、たとえ公務外の私的な時間における事故であっても、公務に対する信用を失墜させたとして、懲戒処分の対象となる可能性があります。
また、民間企業の従業員であっても、悪質な事案の場合にニュースなどで勤務先の社名が報じられてしまうと、会社の評判を落としたとして処分を受けることもあり得ないとはいえません。
ほかにも、加害者が著名人であれば、死亡事故を起こしたということが報道され、自身のイメージが低下してしまうといったことも考えられます。
法律上の責任と異なり、社会的責任は、その人が社会的にどのような立場にあるかによって生じる責任の内容が変わってきます。
場合によっては、法的責任にも劣らないほどの厳しいものとなることもありますので、ハンドルを握る際には常に自覚と緊張感を持たなければなりません。
交通死亡事故の流れ
交通死亡事故が発生すると、次のような流れで手続きが進みます。

①事故発生、捜査
警察が事故の事実を把握すると、捜査が開始します。
捜査には、容疑者を逮捕するケースと、逮捕せずに取り調べの際に容疑者を呼び出す形で進める在宅捜査があります。
警察の捜査は主に、証拠物の収集や、関係者からの聞き取りを書面化して調書を作成するといった形で進んでいきます。
②送検、起訴・不起訴の決定
捜査が終結すると、警察は検察官に対し事件を送検します。
捜査段階で容疑者を逮捕している場合は、容疑者の身柄ごと送検する身柄付きの送検となり、在宅事件として逮捕せずに捜査が進められた場合は、事件記録のみを送検する「書類送検」となります。
事件の送検を受けた検察官は、刑罰を科すのが相当と判断した場合は容疑者を起訴し、その必要がないと判断すると不起訴処分とします。
起訴されると手続きが刑事裁判に移行するのに対し、不起訴処分となった場合は、事件はそこで終結します。
③刑事裁判、判決
刑事裁判では、起訴された容疑者が有罪であるかを審理し、有罪の場合は、裁判官が判決によって刑を言い渡します。
執行猶予付きの判決であれば刑は直ちには執行されませんが、執行猶予がつかない実刑判決の場合は、実際に刑務所で服役するなどして刑の執行を受けることになります。
④刑の執行
執行猶予のない有罪判決が確定すると、刑が執行されます。
実際に罰金を納付したり、刑務所で服役したりすることによって、刑事上の責任を果たすことになります。
加害者が交通死亡事故直後にすべきこと
交通死亡事故は加害者にとっても突然のアクシデントですので、発生直後にはある種のパニック状態となって動揺するのが普通です。
ただし、そのような混乱の中でも、事故の加害者として取るべき行動というものがあります。
間違っても、そのまま逃走するといったようなことはあってはなりません。
以下では、加害者が交通死亡事故の直後にすべきことをご紹介します。
これに違反した場合はより罪が重くなるといった不利益を被ることもありますので、もしもの際の参考にしてください。
道路交通法の義務に従う
道路交通法では、交通事故を起こした際の義務として、「運転の停止」、「負傷者の救護」、「危険の防止」という3つの措置義務を定めています(道路交通法72条)。
またこれらのほか、警察官に対して事故を報告する義務も定められています。
交通死亡事故の加害者は、まず第一に法律の定めている義務を果たす必要があります。
以上の義務の詳細な内容は、次のとおりです。
運転を停止し、周囲の状況を把握する
交通事故が発生した場合、まずは車両の運転を停止して、周囲の状況を把握する必要があります。
道路交通法では、「直ちに車両等の運転を停止して」と定められていますので、一度でも現場を離れてしまうと、「すぐに戻ってくるつもりだった」といった言い分が認められる見込みは低いといえます。
轢き逃げとして重く処罰されることにもなりかねませんので、そのようなことがないよう注意しなければなりません。
負傷者の救護
交通死亡事故が発生した直後、運転を停止した後に最優先で実施すべきなのが、負傷者の救護です。
死亡事故では救護活動に当たる余地がないと思われるかもしれませんが、事故が「死亡事故」であるかは後になって分かることであり、事故直後の段階で判断することはできません。
速やかな救護活動によって被害者が一命を取り留める可能性もありますし、仮にすでに被害者が死亡しているとしても、そのことを素人が独断で決めつけるのは危険です。
また、事故直後に救護活動に尽力しておけば、結果的に被害者が死亡したとしても、そのような態度が後の刑事裁判で有利な事情となることも考えられます。
このようなことから、事故発生直後の救護活動は、何にも増して最優先で行うべきといえます。
実際には、個人で負傷者を救護することには限界もあるでしょうから、被害者の身の安全を確保しつつ救急を要請するという形になることが多いと思われます。
危険防止の措置
道路交通法では、負傷者の救護に加え、道路における危険を防止するための措置を取る義務が定められています。
運転者が危険防止の措置を取らなかった場合、後続の車に追突の危険が生じるなど、被害が拡大するおそれがあります。
そのため、交通事故を起こした際には、道路上の危険を除去して安全を確保する必要があります。
具体的な危険防止措置の内容は、そのときの気象状況や時間帯といった現場の状況によって変わってきますので、一概にはいえません。
一般論としては、可能であれば事故車両を路肩に移動させる、道路上に散乱した危険物を取り除く、後続車を適切に誘導するといった行為により、二次的な被害が発生しないようにするのが適切と考えられます。
警察への通報
道路交通法には、以上の3種の措置義務に加えて、事故の状況を警察に報告する義務が定められています。
道路交通法で警察に報告するものと定められている事項は、以下のとおりです。
- 交通事故が発生した日時及び場所
- 死傷者の数及び負傷者の負傷の程度
- 損壊した物及び損壊の程度
- 事故車両の積載物
- 交通事故について講じた措置
報告すべき項目が多岐にわたりますので、常にこれらの事項を頭に入れておいて事故の場で漏れなく報告するというのは、現実的ではないでしょう。
そこで、事故直後にはひとまず110番通報をして警察に事故の一報を入れ、あとは到着した警察官の質問に答えていけば、自然と上記の事項を網羅して報告義務を果たすことができると思われます。
保険会社への連絡
ここまでご紹介してきた措置義務や報告義務は道路交通法上の義務ですが、これらのほか、加入している保険会社への連絡も忘れてはいけません。
保険の約款には通常、事故の際には事故の状況や損害の発生状況といった詳細を通知するように義務が定められています。
正式な通知は書面で行うことになりますが、多くの保険会社では事故対応のための専用窓口を設けており、保険会社によっては24時間事故受け付けを行っている会社も存在します。
保険会社への通知は、上記の措置義務や報告義務とは異なり、法律上の義務ではなく契約上の義務にすぎません。
ただし、通知を怠っていると適切な補償を受けられない可能性が出てきますので、法律上の義務でないからといって疎かにすることはできません。
まずは電話で構いませんので、早い段階で保険会社にも一報を入れ、その後の手続きについて案内を受けるようにしましょう。
加害者が交通死亡事故後に検討すべきこと
死亡事故を起こした直後には、道路交通法の定めるところに従って、必要な措置や報告をする義務があります。
ここでは、その後の対応として、事件の解決に向けて加害者が検討すべき事項を解説します。
遺族対応などの繊細な問題についても触れていますので、ぜひ参考としてください。
葬儀への出席について
被害者の葬儀には、可能な限り出席します。
葬儀に出席する義務があるわけではありませんが、葬儀は加害者が被害者に対する弔意を表明する最初の機会であり、出席しなかった場合、謝罪の意思がないものと受け取られることにもなりかねません。
その後の示談交渉を円滑に進める上でも、葬儀に出席して謝罪の言葉を伝えるのは重要といえます。
その反面、直接遺族と対面するとなると、遺族の気持ちを乱すことになるおそれもありますので、可能であれば、保険会社の担当者や依頼する予定の弁護士などを同伴して行くと、緩衝材のような役割が期待できるでしょう。
ただし、死亡事故の遺族の中には、加害者への処罰感情が大変強く、葬儀への列席を拒否されるケースも少なくありません。
そのような場合は、遺族のご意向を尊重し、葬儀への出席は控えるのが無難です。
拒否されているにもかかわらず、どうしても直接謝罪しないと気が済まないからと強引に押し掛けたのでは、遺族よりも自分の気持ちを優先していることになってしまい不適切です。
かえって遺族の感情を害してしまったのでは本末転倒ですので、葬儀には事前に遺族の許可を得て参列することが望ましいといえるでしょう。
香典について
香典は、故人の霊前に供える花や線香の代わりとして渡す金銭であり、葬儀の際に持参するのが一般的です。
香典の金額は、地域によっては独自の慣習が存在するケースもありますが、一般的には、親類縁者であれば1万円から10万円程度、それ以外の友人関係などであれば5千円から1万円程度が相場といわれます。
交通事故の加害者は特殊な事例ですので、いくらを包むべきかは悩ましい問題でもあります。
被害者の命をうばっているという加害者の立場上、それなりの金額でなければ失礼に当たるとはいえますが、香典はあくまで葬儀へ列席する上でのマナーとして持参するものです。
法律上の賠償責任は別途果たす必要がありますので、香典の名目であまりに高額の金践を渡すのも相応しいとはいえません。
このようなことから、香典の金額に正解があるわけではありませんが、保険会社の対人臨時費用特約における香典代では10万円から20万円となっている例が多いようですので、これがひとつの目安になるとはいえるでしょう。
謝罪について
死亡事故を起こした加害者にとって、被害者の遺族に対して謝罪することは、きわめて重要です。
突然家族を失うことになった遺族の悲しみは察するに余りあるものであり、謝罪したからといって、簡単に受け入れてもらえるとは限りません。
しかしたとえそうであっても、被害者に対して誠心誠意謝罪の気持ちを伝えようとすることは、加害者にできる精一杯の償いのひとつといえます。
また、被害者に対して謝罪しているという事実は、事件の処分を決めるにあたって有利に考慮されるのが一般的です。
裁判で有利になるために謝罪するというものではもちろんありませんが、きっちり反省していることを態度で示しておくことで、裁判官も加害者が反省しているということを認定しやすくなるとはいえるでしょう。
なお、遺族の中には、謝罪の意向を伝えても拒否される方もいらっしゃいます。
そのようなときは、手紙の形で謝罪文をお渡しすることを検討してもよいでしょう。
謝罪文について
被害者遺族に対して謝罪の気持ちを表明する際には、謝罪文を書く方法も有効です。
謝罪文を書くにあたっては、事故の原因と真摯に向き合い反省を深めるとともに、被害者の悲しみに寄り添うことが重要です。
定型句をならべただけの紋切り型の謝罪文では、反省の気持ちは伝わらず、遺族の感情を逆なでする結果にもなりかねません。
また、謝罪文が弁解めいていたり言い訳がましかったりするのも、火に油を注ぐようなものですので、あってはなりません。
手紙自体ふだん書き慣れていないという方も多いでしようから、このような「自分視点」の文章になってしまうのを避けるためにも、第三者に意見やアドバイスを求めるのがよいでしょう。
刑事事件を多く取り扱っている弁護士であれば、被害者対応の経験も豊富であり、謝罪文の文面についても適切かどうかを判断できますので、謝罪文は事前に弁護士に見てもらうことをお勧めします。
示談交渉を行う
死亡事故で、不起訴や執行猶予といった寛大な処分となる可能性をあげるためには、被害者遺族と示談することが重要です。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪するとともに、損害を賠償して和解することをいいます。
示談が成立していれば、損害賠償責任はすでに果たされ被害者の許しを得ていることになりますので、民事事件としてはすでに解決しているといえます。
示談が成立しているのであれば、検察官としてもあえて裁判を開始して刑罰を科す必要まではないと判断して、不起訴処分とすることが期待できるのです。
もちろん、示談が成立していればそれで不起訴が確約されるというものではありません。
容疑者の起訴・不起訴は、あくまで総合的に判断されるものです。
悪質性が高い事案であれば、たとえ示談が成立していても、そのことだけで処罰を免れさせるのは適当ではないと判断されて起訴されるケースもあり得ます。
とはいえ、たとえ不起訴にはならないまでも、示談が成立しているのであれば、それがマイナスとなることはありません。
起訴された場合、有罪判決を回避することは難しいかもしれませんが、過失運転致死罪であれば、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性は十分にあります。
中でも、示談が成立していれば、執行猶予を獲得できる可能性はさらに高まることが期待できます。
この点からも、不起訴処分の獲得はもちろんのこと、それ以外の面においても、被害者と示談することは重要といえるのです。
示談についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。
刑事事件に強い弁護士に相談する
死亡事故を起こした加害者は、刑事事件に強い弁護士に依頼することも重要になってきます。
死亡事故における示談の重要性はすでに解説したとおりですが、死亡事故のような重大な事件で、被害者との示談を成立させることは容易ではありません。
家族の命をうばわれた遺族にとって、加害者に対する処罰感情は特に強いケースが多く、被害者の納得を得て示談を成立させるのは非常に困難なのです。
刑事事件に強い弁護士であれば、死亡事故のように被害者の処罰感情が強いケースでの示談交渉についても豊富な経験がありますので、被害者の感情に配慮した丁寧な示談交渉が期待できるのです。
示談を成立させ事件を円満に解決するためにも、ぜひ刑事事件に強い弁護士への相談をご検討ください。
刑事事件における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。
死亡事故と加害者に関するQ&A
![]()
死亡事故で加害者がもらえるお金は?
このようなケースでは、加害者側がけがや車両の破損等の損害を負っていれば、その部分に関しては、相手方が加害者ということになります。
加害者が被った損害のうち、過失割合に応じた部分を相手方に請求することは可能です。
なお、保険に加入していれば被害者に対する損害賠償は保険から給付されますが、通常は保険会社から直接相手方に支払われるため、加害者が受領することは基本的にありません。
![]()
交通事故で加害者が死亡した場合、保険はどうなるのか?
したがって、加害者死亡の事案であっても、保険会社に損害賠償を請求することになります。
![]()
死亡事故の加害者は免許を再取得できる?
欠格となる期間は、今回の件だけでなく、これまでの違反による点数の累積や、前歴の回数なども考慮して決定されます。
死亡事故の場合、悪質でない事案でこれまでに処分歴がなかったとしても、1年間の欠格期間が生じ、悪質なケースで前歴もあるようなケースですと、欠格期間は最長で10年に及ぶこともあります。
まとめ
この記事では、死亡事故の加害者について、加害者が負う責任の内容や、事故後の流れ、事故後において加害者がとるべき対応などを解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- 交通死亡事故では、相手を死亡させた側が加害者となり、加害者には法律上、民事責任、刑事責任、行政上の責任の3つの責任が生じる。
- 交通死亡事故は、被害者の死亡という最悪の結果を招いたものであり、長期にわたる服役や多額の損害賠償のように、刑事上も民事上も重い責任を問われる可能性がある。
- 交通死亡事故の加害者は、事故直後においては、道路交通法の定めるところにしたがって、救護措置や警察の報告といった義務を果たすほか、保険会社の連絡も忘れてはならない。
- 交通死亡事故の加害者は、被害者遺族の意向を尊重しつつ、葬儀に列席したり謝罪文を書いたりして誠心誠意謝罪すべきである。
- 交通死亡事故では、刑事事件に強い弁護士に示談交渉をはじめとする弁護士活動を依頼することが有効である。
当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。
まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。