未必の故意とは?認識ある過失との違いをわかりやすく解説
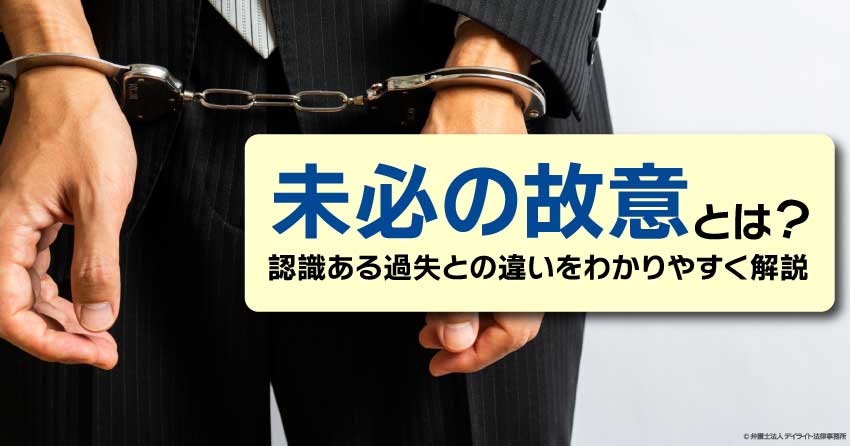
未必の故意(みっひつのこい)とは、犯罪の結果が生じる可能性を認識しながら、これを認容している状態を意味し、刑法上の故意として扱われる概念です。
この概念は、犯罪の成立要件である「故意」の一種であり、法的責任の程度に大きく関係してきます。
刑事事件において、行為者に未必の故意があったと認定されると、故意犯として処罰され、過失犯と比べて重い刑罰が科される可能性があります。
そのため、未必の故意が認められるかは、刑事責任を大きく左右する重要な争点になることがあります。
この記事では、未必の故意について、その意味や認定基準、具体例や認められない例、そして認定された場合の法的影響などを弁護士が解説します。
未必の故意は少し難しい概念ではありますが、丁寧に読み解けば基本的な理解をすることは可能です。
未必の故意に関心をお持ちの方は、ぜひこの記事を参考になさってください。
未必の故意とは?
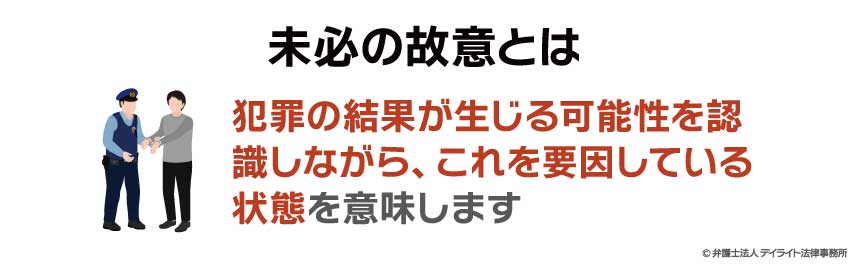
未必の故意(みっひつのこい)とは、犯罪の結果が生じる可能性を認識しながら、これを認容している状態を意味します。
故意とは?
法律の世界で「故意」とは、「わざと、意図的に」という意味です。
故意は、「うっかり、不注意で」を意味する「過失」と対になる概念です。
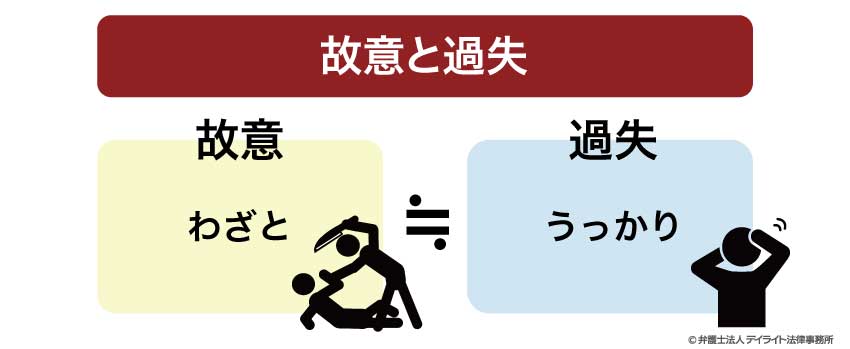
たとえば、車で人を轢いて死なせるというシチュエーションでは、その人を殺そうという意図を持って実行したのであれば故意が認められるのに対し、不注意で事故を起こしたのであれば過失となります。
なぜ故意が重要か
ある行為が犯罪であるかを考えるに当たって、故意は重要な意味を持ちます。
刑法には、「故意犯処罰の原則」という考え方があります。
これは、犯罪行為として刑事責任を問われるのは原則として故意の行為に限られ、罪を犯す意思がない場合には処罰しないというものです。
この原則により、過失による行為については、過失の場合も処罰するという例外的な規定が存在しない限り、犯罪とはなりません(刑法38条1項)。
参考:刑法|e-Gov法令検索
犯罪とわかりながらあえてやったという故意の犯行と異なり、過失の場合は不注意ですので、多かれ少なかれ誰でも起こす可能性があるものです。
そこで、犯罪として処罰するのは故意犯が原則とされ、過失の行為については、人の死傷のような重大な結果を生じさせるものに限り、例外的に処罰規定が置かれています。
たとえば、前記の車の例ですと、故意の場合は殺人罪、過失の場合は過失運転致死罪となります。
他方で、他人の物を意図的に破壊すれば器物損壊罪になるのに対し、不注意で壊してしまった場合には犯罪とはなりません。
なぜなら、「過失器物損壊罪」のような犯罪が法定されておらず、故意犯処罰の原則に従って、故意の損壊行為のみが犯罪とされるためです。
このように、故意の有無は、ある行為が犯罪となるかどうか、また罪になるとしてどのような犯罪が成立するかを左右する重要な事項なのです。
なお、過失で他人の物を壊した場合、損害賠償の問題があります。
これは、民事責任の問題であり、刑事責任ではありません。
未必の故意の意味
故意には種類があり、未必の故意もそのひとつです。
未必の故意は、「犯罪の結果が生じる可能性を認識しながら、これを認容している状態」を意味します。
簡略化して、「犯罪結果の認識・認容」と表現されることもあります。
これだけを見ても、何を意味しているか分かりづらいと思いますので、器物損壊を例に考えてみましょう。
たとえば、不注意によって他人の物を壊してしまっても、それは過失によるものですので、器物損壊罪にはならないのでした。
他方で、他人の物をわざと壊すと、それは意図的な破壊行為であり故意があるため、器物損壊罪となります。
このように、犯罪に当たることを確信している故意を、「確定的故意」といいます。
対して未必の故意は、積極的に破壊する意図まではないものの、「もっと丁寧に扱わないと壊れるかもしれない」との認識の下、「それならそれで構わない」と思って物を雑に扱うような場合に認められます。
「犯罪の結果が生じる可能性を認識しながら、これを認容している状態」というのが、未必の故意の定義です。
これに当てはめてみると、「壊れるかもしれない」というのが「犯罪の結果が生じる可能性の認識」であり、「それでも構わない」というのが「犯罪結果の発生を認容している状態」となります。
別の例では、人を刃物で刺す際に、「殺してやろう」と思って刺すのが確定的故意で、「殺すというよりは痛めつけてやりたいだけだが、仮に死んでも別に構わない」というのが未必の故意となります。
未必の故意では、他人の物を壊したり、相手が死んだりといった犯罪の結果が生じることについて、それで構わないと「認容」しているところがポイントです。
未必の故意が認められるのは、結果が発生し得ることを分かっていながら、行為を思いとどまることなく実行した場合です。
このような心理状態は、誰にでも起こり得る不注意とは一線を画するものです。
未必の故意は、犯罪となる可能性を認識しながらあえてやっている点で、故意の一種として法的な非難に値するといえるのです。
未必の故意と認識ある過失との違い
未必の故意とよく似た概念として、「認識ある過失」というものがあります。
認識ある過失とは、犯罪の結果が発生する可能性を認識しつつ、そのようなことにはならないと軽々しく信じてしまうことをいいます。
たとえば、自動車を異常な高速度で運転する場合において、誰かを傷つけてしまう可能性を認識しつつ、「それでも構わない」と考えれば未必の故意です。
これに対して、「自分の運転技術なら回避できるから大丈夫だ」と軽信するのが、認識ある過失です。
未必の故意と認識ある過失は、いずれも犯罪結果が生じる可能性を認識していますが、それを認容しているかどうかが異なります。
結果発生を認識し、かつ認容しているのが未必の故意で、結果発生を認識しているが認容はしていないのが、認識ある過失です。
認識ある過失で被害を生じさせた場合、軽率である点は非難すべきですが、過失は過失ですので、故意犯にはなりません。
未必の故意が認められる具体例
未必の故意の概念を理解するためには、具体的にどのような場合に未必の故意が認められるのかを知ることが役立ちます。
実際の裁判では、行為の性質や状況、行為者の言動などさまざまな要素から未必の故意が判断されます。
ここでは、未必の故意が問題となりやすい犯罪類型と、実際に未必の故意が認定された裁判例を見ていきましょう。
未必の故意が問題となりやすい犯罪
実務上、未必の故意が特に問題となりやすい犯罪としては、人の死傷という結果が伴う犯罪があります。
人の死傷という結果の発生を認容していたかによって、その結果に対する故意犯が成立するかが変わるためです。
故意の中でも、特に人の死という結果に対する故意を、「殺意」といいます。
人に暴行を加えた結果相手を死なせてしまった場合、相手が死んでもかまわないとの認容があった場合には殺人罪、認容していなかった場合には傷害致死罪となります。
未必の故意は、犯罪結果を認容していたという内心の主観ではありますが、未必の故意があったか否かは、客観的な事情を考慮して判断されます。
たとえば、心臓をめがけて何度も刃物で突き刺したような事案で、「殺すつもりはなかった」と弁解したところで、そのような主張が認められる可能性は限りなく低いと考えられます。
本当に殺すつもりがないのであれば、致命傷にならないようなところを狙うのが普通であり、心臓を狙って刺すことの説明がつかないためです。
未必の故意が認定された裁判例
未必の故意が認定された有名な裁判例として、騒音による傷害事件があります。
この事件は、隣家に向かって大音量のラジオや目覚まし時計のアラーム音をおよそ1年半にわたって鳴らし続け、頭痛や睡眠障害、耳鳴り等の傷害を発症させたという事件です。
一般的な傷害事件が、直接的な暴力行為によって怪我を負わせるものであるのに対し、本件は「音」という目に見えない方法による嫌がらせである点に特徴があります。
結論として、この事件では、頭痛等の発症に対する未必の故意が認定されました。
それだけの期間にわたって騒音を鳴らし続ければ、頭痛や耳鳴りが生じることは、十分あり得ると考えられます。
そのような危険性をはらんだ行為を継続した以上、被害者に頭痛等の症状が生じたとしても、それでかまわないという「認容」があったと認められたのです。
未必の故意が認められない例
未必の故意が認められるためには、行為者が結果発生の可能性を認識し、かつそれを認容していることが必要です。
しかし、行為時の状況から、未必の故意が否定される場合もあります。
故意は内心の問題であるが、その認定は客観的な事情に基づいて行われる、というポイントがありました。
つまり、未必の故意が認められない例とは、結果の発生を認容していたことがうかがわれるような事情が存在しない例ということができます。
たとえば、人を素手で一発殴ったところ、相手がバランスを崩して転倒し、頭を打って死亡したとします。
このような場合、人を一回殴っただけで相手が死ぬというのはレアなケースといえます。
そのため、そのような行為に出たことをもって、死の結果を認容していたとまでは言い難いと判断されるのが一般的と思われます。
このように、行為自体の危険性が低いか、行為自体は危険であるが、その危険が現実のものとならないように予防策を講じていたような場合には、結果を認容していないとして未必の故意が認められない可能性があります。
未必の故意が認められなかった実際の事例としては、危険運転致死傷罪の成立が否定された事案があります。
この事件は、自動車を時速146キロメートルで走行させて死傷事故を引き起こしたものです。
この事件では、未必の故意が認定されませんでした。
時速146キロメートルでも危険運転致死にならないというと、意外な印象があるかもしれません。
ポイントは、危険運転が成立するのは、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」であるという点です。
危険運転となるには、単に高速度であるだけでは足りず、その速度が進行を制御することが困難なものであることも必要です。
そのため、たとえ客観的には高速での走行であったとしても、運転者が進行の制御が困難であると認識していなければ、故意は認められないことになります。
この事故は、被害車両が被告人車両の進路に進出してきたために、自車の進路が狭くなって起こったものです。
そのような事態が生じることは事前に想定できるものではないため、「進行を制御することが困難な」速度での走行であることについて、未必的にも故意はないと判断されました。
この事件では、未必の故意が認定できる事案ではないかとの見方もありますが、裁判所としては、制御困難であることを認容していたとまでの認定はできなかったものと思われます。
未必の故意が認められることによる不利益
未必の故意が認められることには、不利益があります。
未必の故意が認められることによる重大な不利益は、故意犯が成立することです。
刑法における故意犯処罰の原則により、過失犯の処罰規定が特に置かれていない限りは、故意が認められなければ犯罪として処罰されません。
また、過失犯が定められている場合でも、その刑は故意犯と比べて格段に軽いのが一般的です。
たとえば、殺人罪(刑法199条)は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と規定されています。
これに対し、業務上過失致死罪(刑法211条)は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と規定されています。

どちらも、結果だけ見れば同じ「人の死」ではありますが、未必の故意による殺人と認定されるか過失致死と認定されるかで、刑罰の重さが大きく異なるのです。
意図的に人を殺した場合と過失で人を死なせた場合とでは、たとえ結果が同じであっても、前者の方がはるかに重罪であることは、感覚的にも納得いただけるところかと思います。
故意犯と過失犯では非難の程度が大きく異なることから、未必の故意が認められると、厳しい処分を受けることが予想されます。
これは、字面上の法定刑が異なるということにとどまりません。
一般論ではありますが、重い刑が定められている犯罪の方が、より逃亡のおそれが高いと判断されやすく、逮捕や勾留といった身体拘束を受けやすくなります。
また、実際の処分としても、過失犯であれば不起訴や罰金、執行猶予といった軽い処分で済む可能性があるところが、故意犯となったばかりに実刑判決となるといったこともありえます。
社会的な評価を考える上でも、やはり故意犯のほうが、より強い非難が向けられることになります。
未必の故意を、故意と過失の中間のような感覚で捉えている方がいらっしゃるとしたら、それは誤りです。
未必の故意は故意の一形態であり、これが認められると、故意犯として厳しい法的責任が生じるのです。
未必の故意のよくあるQ&A
![]()
未必の故意が殺人未遂に与える影響とは?
たとえば、相手をナイフで刺して怪我をさせた場合、殺人未遂又は傷害となります。
そのいずれが成立するかは、死の結果に対する未必の故意、すなわち殺意の有無によって変わります。
被害者の死を認容していたと認められれば殺人未遂となり、そこまでの認容が認められなければ傷害罪となります。
まとめ
この記事では、未必の故意について、その意味や認定基準、具体例や認められない例、そして認定された場合の法的影響などを解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- 未必の故意とは、犯罪結果が発生する可能性を認識しながら、それを認容して行為に出ること意味し、刑法上の故意の一種である。
- 犯罪として処罰されるのは原則として故意犯であり、過失犯が処罰されるのは例外的な場合に限られる。
- 未必の故意と認識ある過失の違いは、結果発生の可能性を認識した上で「それでもよい」と認容するか、「自分なら回避できる」と信じるかの点にある。
- 未必の故意は内心の問題であるため立証が難しいが、行為の危険性や行為者の言動などの諸事情から総合的に判断される。
- 未必の故意が認められると、故意犯となり重い法的責任が発生する。
当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。
まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか










