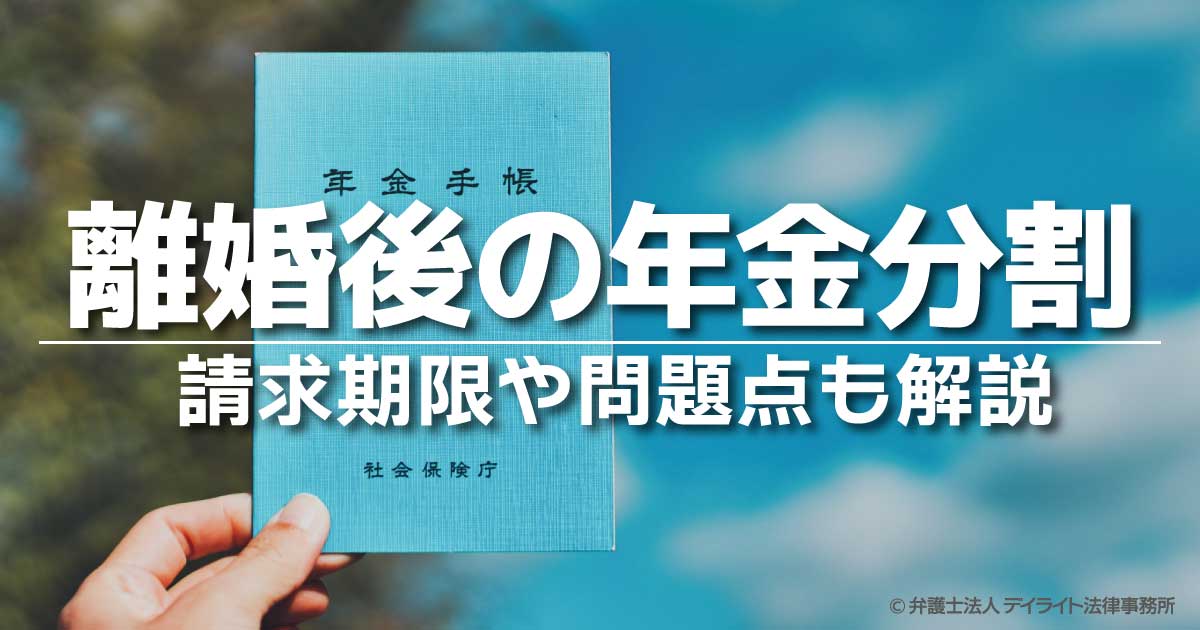離婚で年金分割をしないとどうなる?具体例でわかりやすく解説

離婚で年金分割をしないと、将来もらえる年金の額が少なくなる可能性があります。
年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割する制度です。
年金分割をしないと、自分に厚生年金の保険料納付実績がない場合(専業主婦の方など)は、老後に厚生年金を受け取ることができません。
他方で、年金分割で相手の保険料納付実績を分割してもらえば、自分に保険料納付実績がない場合であっても厚生年金を受け取ることができるようになります。
共働きの場合でも、相手との収入差が大きい場合は、年金分割をしないと夫婦間で年金の受給額に大きな格差が生じてしまう可能性があります。
他方で、年金分割を行えば、収入差が大きい場合でも結婚期間中の保険料納付実績に対応する報酬比例部分については相手と同額(50%で分割する場合)受け取ることができるようになります。
年金の受給額は老後の生活設計に大きく関わるため、年金分割の影響を知っておくことは重要です。
そこで、ここでは年金分割をしないとどうなるか、その影響について具体例を用いて解説していきます。
離婚で年金分割をしないとどうなる?
離婚で年金分割をしないと、将来もらえる年金の金額が少なくなる可能性があります。
年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割する制度です。
厚生年金とは、会社員や公務員の方が加入する年金です。
例えば、夫が会社員で、妻が専業主婦の場合は、夫のみが厚生年金に加入し保険料を納め、夫のみが厚生年金の受給者となります。
このケースで、夫婦が離婚する場合に年金分割をしないと、将来は夫のみが厚生年金を受け取ることとなり、保険料納付実績がない妻が厚生年金を受け取ることはできません。
一方、年金分割をする場合は、妻は夫の保険料納付実績の最大半分(50%)を自らのものとすることができます。
そのため、将来は夫のみならず、妻も分割を受けた保険料納付実績に基づいて厚生年金を受け取ることができるようになります。
共働きで夫婦双方が厚生年金に加入している場合でも、夫婦の間に収入差がある場合は、年金分割をしないと将来受け取る年金額に格差が生じます。
厚生年金の受給額は保険料納付実績によって決まりますが、保険料納付実績は、給料が高いほど、そして加入期間(働いていた期間)が長いほど多くなるためです。
一方、年金分割をする場合は、夫婦の保険料納付実績を最大半分(50%)ずつに分けることができます。
そのため、共働きの場合でも収入差がある(相手の方が多い)場合は、年金分割を行うことで将来自分が受給できる年金額が増加することになります。
年金分割とは?
年金分割とは、離婚に伴い、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割する制度です。
実際にもらえる年金それ自体を分け合うものではなく、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付記録(年金受給額の算定基礎となるもの)を分けるものです。
例えば、結婚期間中の厚生年金の保険料納付記録が夫8000万円、妻2000万円の場合、その総額1億円が分割の対象となります。
このケースで、仮に50%の割合で年金分割をすると、それぞれの保険納付記録は夫5000万円、妻5000万円と改定されることになります。

年金分割についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
年金分割には2種類ある
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割
合意分割とは、分割割合(按分割合)を夫婦の合意によって決めるものです。
分割割合の上限は2分の1(50%)、下限は分割を受ける側が年金分割により自分の標準報酬(保険料納付記録)が減額されることのない割合となります。
もっとも、ほとんどのケースでは2分の1で合意され、2分の1以外となるケースは稀です。
夫婦間で分割割合の合意ができない場合は、家庭裁判所の手続き(多くの場合は審判)を申立て、裁判所で分割割合を定めます。
裁判所が分割割合を定める場合も、ほとんどのケースで2分の1となります。
分割割合が決まったら、原則として夫婦本人(又は代理人)が2人で一緒に年金事務所に出向いて年金分割の手続きを行います。
ただし、公証役場や家庭裁判所で作成した合意に関する書類(公正証書、調停調書、審判書又は判決書など)があれば夫婦の一方だけでも手続きをすることができます。
3号分割
3号分割とは、第3号被保険者の請求に基づき、第3号被保険者であった期間の標準報酬について、自動的に2分の1の割合で分割されるものです。
第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金保険の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。
専業主婦の方などがこれに該当します。
3号分割は、第3号被保険者の請求によって自動的に2分の1の割合で分割されるものであるため、夫婦間での合意は必要なく、裁判所が関与することもありません。
また、分割請求の手続きは、第3号被保険者だった方が単独で行うことができます。
ただし、3号分割は2008年4月に始まった制度であるため、2008年4月1日以降の保険料納付実績のみが対象となります。
それ以前の保険料納付実績については、合意分割を行う必要があります。
また、3号分割ができるのは、第3号被保険者であった期間に限られます。
そのため、現在は専業主婦でも、結婚期間中に会社員などとして働いていたことがある場合は、その働いていた期間の保険料納付実績については合意分割をする必要があります。
なお、合意分割の請求をした場合に、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、合意分割だけを請求した場合でも、3号分割の対象となる期間が含まれるときは、その期間については先に3号分割が行われることになります。
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 対象となる期間 | 婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者(※)であった期間 |
| 分割の対象 | 夫婦双方の婚姻期間中の標準報酬総額の合計額 | 2008年4月1日以降の婚姻期間中の第2号被保険者の標準報酬総額 |
| 分割の割合 | 2分の1が上限(ただし、2分の1以外になる場合は稀) | 2分の1 |
| 合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要(請求すれば自動的に分割される) |
| 手続き | 夫婦(裁判所の決定をもらった場合は請求する人)が年金事務所で手続きをする | 第3号被保険者だった人が年金事務所で手続きをする |
年金分割には期限がある
年金分割は、合意分割・3号分割ともに離婚後(離婚成立日の翌日から)2年以内に請求しないと請求できなくなってしまいます。
ただし、離婚後2年を経過する前に家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判または調停を申立てをすれば、事件係属中に2年を経過してしまっても請求権は失われません。
しかし、この場合は、審判確定または調停成立後1か月以内に年金分割を請求する必要があります。
年金分割をしないときの影響を事例で解説
ここでは、年金分割をする場合としない場合でどのくらい厚生年金の給付額が変動するかについて、事例を用いて解説していきます。
各事例の前提条件
老齢厚生年金の報酬比例部分(年金分割により金額が変わる部分)のみを示し、老齢基礎年金や老齢厚生年金の経過的加算などは含まないものとします。
将来支給される年金の全額を示すものではありませんのでご注意ください。
- 夫は結婚期間中ずっと厚生年金に加入していたこととします。
- 分割の割合は50%とします。
- 報酬比例部分の上率は「5.481/1000」で算定します。
※2003年3月以前の加入期間については乗率は「7.215/1000」となりますが、ここでは便宜上一律に「5.481/1000」を用いることとします。 - 報酬比例部分は結婚期間や給料の金額によって異なります。ここでは、結婚期間が10年・20年・30年の場合、給料が月平均30万円程度・50万円程度の場合(※)を想定して概算額を示すこととします。
※平均標準報酬月額が30万円・50万円の場合を想定
平均標準報酬月額の算出の際には再評価(現在価値に換算)が入るため、実際の給料の月平均と平均標準報酬月額の金額は必ずしも一致しませんが、ここでは便宜上一致するものとして計算します。
専業主婦のケース
妻が専業主婦であるケースでは、年金分割の前後で次のような違いが生じます。
夫の給料の月平均が30万円程度の場合
| 結婚期間 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分割前 | 分割後 | |||
| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |
| 10年 | 197,316円 | 0円 | 98,658円 | 98,658円 |
| 20年 | 394,632円 | 0円 | 197,316円 | 197,316円 |
| 30年 | 591,948円 | 0円 | 295,974円 | 295,974円 |
※金額は1年の総支給額となります。
夫の給料の月平均が50万円程度の場合
| 結婚期間 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分割前 | 分割後 | |||
| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |
| 10年 | 328,860円 | 0円 | 164,430円 | 164,430円 |
| 20年 | 657,720円 | 0円 | 328,860円 | 328,860円 |
| 30年 | 986,580円 | 0円 | 493,290円 | 493,290円 |
※金額は1年の総支給額となります。
妻が専業主婦の場合、妻自身に厚生年金の保険料納付実績はないため、年金分割をしないと妻は老齢厚生年金をもらうことはできません。
一方、年金分割で夫の保険料納付実績の分割を受ければ、老齢厚生年金の報酬比例部分(結婚期間の保険料納付実績に対応する部分)については、夫と同額を得ることができるようになります。
このように、専業主婦の場合は、年金分割をする・しないで大きな違いが生じることになります。
共働きのケース
妻も会社員で厚生年金に加入しており、例えば月平均20万円程度の収入がある場合は、年金分割の前後で次のような違いが生じます。
夫の給料の月平均が30万円程度・妻の月平均が20万円程度の場合
| 結婚期間 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分割前 | 分割後 | |||
| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |
| 10年 | 197,316円 | 131,544円 | 164,430円 | 164,430円 |
| 20年 | 394,632円 | 263,088円 | 328,860円 | 328,860円 |
| 30年 | 591,948円 | 394,632円 | 493,290円 | 493,290円 |
※金額は1年の総支給額となります。
夫の給料の月平均が50万円程度・妻の月平均が20万円程度の場合
| 結婚期間 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分割前 | 分割後 | |||
| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |
| 10年 | 328,860円 | 131,544円 | 230,202円 | 230,202円 |
| 20年 | 657,720円 | 263,088円 | 460,404円 | 460,404円 |
| 30年 | 986,580円 | 394,632円 | 690,606円 | 690,606円 |
※金額は1年の総支給額となります。
共働きの場合は、年金分割をしなくても妻も老齢厚生年金を受け取ることができます。
しかし、夫と収入差がある場合は、妻のもらえる金額は夫のそれよりも少額になります。
結婚期間が長いほど、そして収入差があるほど、夫と妻の年金額の差は大きくなります。
一方、年金分割をすれば、夫と収入差がある場合でも、老齢厚生年金の報酬比例部分(結婚期間の保険料納付実績に対応する部分)については、妻も夫と最大で同額をもらうことができるようになります。
このように、共働きの場合でも年金分割の前後で大きな差が生じることがあります。
年金分割額をシミュレーターで簡単に計算!
当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
シミュレーターはこちらからご利用ください。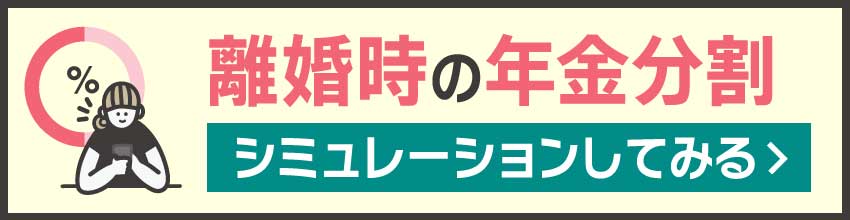 正確な金額を確認されたい方は年金事務所にお問い合わせください。
正確な金額を確認されたい方は年金事務所にお問い合わせください。
年金分割をしないことについての知恵袋的Q&A
![]()
年金分割しない方がいい場合ってどんな場合?
このように、年金分割による経済的なメリットが小さい場合は、手続きにかかる費用や労力の節約を優先し、年金分割をしないという選択肢もありうるでしょう。
![]()
離婚後、年金分割をしたくないのですが、拒否できますか?
3号分割の場合は、相手が手続きをすれば自動的に(強制的に)分割がされますので、拒否することはできません。
合意分割の場合は、分割割合を合意する必要があり、この合意を拒むこと自体は可能です。
しかし、合意を拒んだとしても、相手が家庭裁判所に審判を申し立てれば、裁判所が分割割合を定めることとなります。
そして、特段の事情がない限りは、50%の割合が定められることになります。
裁判所により分割割合が定められれば、相手は単独で年金分割の請求手続きを行えるようになります。
まとめ
以上、離婚で年金分割をしないとどうなるかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
年金分割をしないと、将来もらえる年金の金額が少なくなる可能性があります。
特に、結婚期間が長い場合や専業主婦の場合、共働きでも収入差が大きい場合は、年金分割をする場合としない場合で年金受給額に大きな差が生じる可能性があります。
年金受給額は老後の生活設計に影響を及ぼすため、年金分割を請求できる場合は期限内に手続きをすることが大切です。
年金分割の制度はわかりにくい面もありますので、お困りの場合は専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、年金分割について、専門知識とノウハウを共有しております。
離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?