
遺言の書き直しは、遺言者が生きている間は、いつでも何度でも自由です。
ただし、遺言の書き直しは、遺言の方式に従うことが必要となります。
ここでは、遺言の書き直しの方法について、弁護士がわかりやすく解説しています。
ぜひ参考になさってください。
遺言の書き直しはできる?
遺言の書き直しは、遺言者が生きている間は、いつでも何度でも自由です。
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています(1022条)。
引用:民法|e-GOV法令検索
この遺言を撤回する権利、すなわち書き直す権利は、放棄することができないとも定められており、遺言の撤回の自由は強く守られています。
遺言の書き直し(撤回)は誰ができるの?その方式は?
遺言の撤回(書き直し)は、遺言者である本人のみが行うことができます。
他の人が代理で撤回することはできませんし、相続人が撤回することもできません。
遺言によって、前の遺言を撤回する場合には、「遺言の方式に従って」行われなければなりません。
「遺言の方式に従って」撤回する場合には、前の遺言と撤回遺言の方式が異なっていても構いません。
したがって、例えば、公正証書遺言を以前に作っていたとして、これを新しく作った自筆証書遺言で撤回することもできるということです。
遺言の方式とは?
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれ方式があります。
遺言はこの方式にしたがって作成しなければなりません。
遺言の撤回とみなされる場合ってどういう場合?
撤回の意思表示が無い場合でも、一定の事実があったときに遺言の撤回があったものとみなされます。
遺言の撤回があったものとみなされるのは以下の場合です。

- ① 前の遺言の内容と抵触する遺言がされた場合
- ② 遺言と抵触する生前処分がされた場合
- ③ 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合
- ④ 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合
具体例を挙げて解説していきます。
具体例 遺言の撤回とみなされる例
あなたには子Aと子Bがいて、遺言①に以下のように書いていたとします。
- AにX不動産を遺贈する(AにX不動産を相続させる)
- BにYカメラを遺贈する(BにYカメラを相続させる)
その後に、以下のようなことが起こったとしましょう。
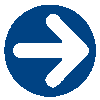 あなたが新たに遺言②に、BにX不動産を遺贈するとの遺言を書いた場合
あなたが新たに遺言②に、BにX不動産を遺贈するとの遺言を書いた場合X不動産について、遺言①の「Aに遺贈する」という部分と、遺贈②の「Bに遺贈する」という部分が抵触している状態になっています。
遺言者は、遺言の方式に従って、その一部または全部を撤回することができるとされていますので、遺言①の「Aに遺贈する」という内容は撤回されたことになります(民法1022条、1023条1項)。
死後に複数の遺言が発見された場合にも、一番新しく作成された遺言が優先しますので、新しい日付の遺言が前の日付の遺言の内容と抵触する場合は、前の遺言の抵触する部分は撤回したものとみなされます。
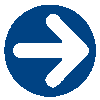 あなたが生前にX不動産をCに売却した場合
あなたが生前にX不動産をCに売却した場合X不動産について、「Aに遺贈する」という内容と、生前にCに売却するという事実は、X不動産の処分というところで抵触をしてしまっています。
このような場合にも、抵触をしている部分は撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
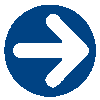 あなたが、遺言①をシュレッダーにかけた場合
あなたが、遺言①をシュレッダーにかけた場合遺言書自体が遺言者によって破棄されています。
遺言者がこれを遺言書であるとわかって破棄する意思で破棄をしたときには、破棄した部分について、遺言が撤回されたものとみなされます(民法1024条前段)。
遺言①の全てをシュレッダーにかけた場合には、遺言①は全て撤回されたということになります。
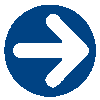 あなたが、生前にYカメラが壊れたので捨てた場合
あなたが、生前にYカメラが壊れたので捨てた場合Yカメラを生前にあなたが捨てています。
この場合にも、Yカメラの部分(破棄した部分)について、遺言が撤回されたものとみなされます(民法1024条後段)。
このように、一度書いた遺言は撤回することができますし、その遺言に抵触する行為などがなされることにより、一度書いた遺言が撤回したものとみなされることになります。
終わりに
 遺言を書くのに早すぎるということはありません。
遺言を書くのに早すぎるということはありません。
一度書いた遺言の内容が、状況の変化に応じ、適しなくなることもありますが、そのときは適切な方法で書き直すことにより、その時々の状況に応じた遺言を残すことが可能です。
遺言書作成をご検討の方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。


