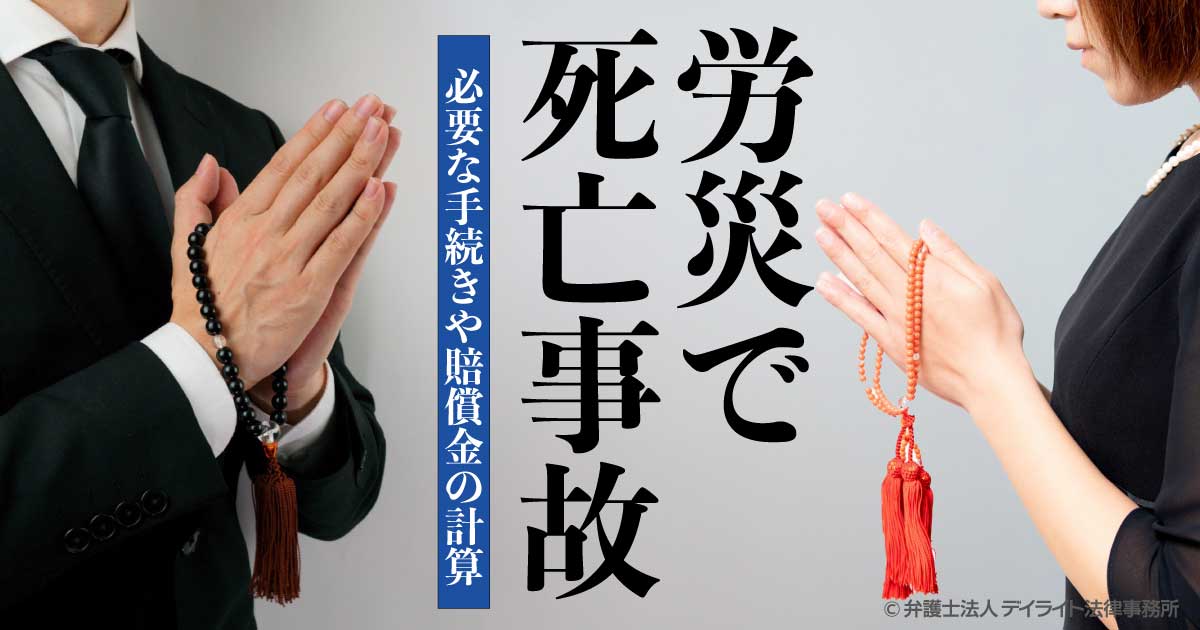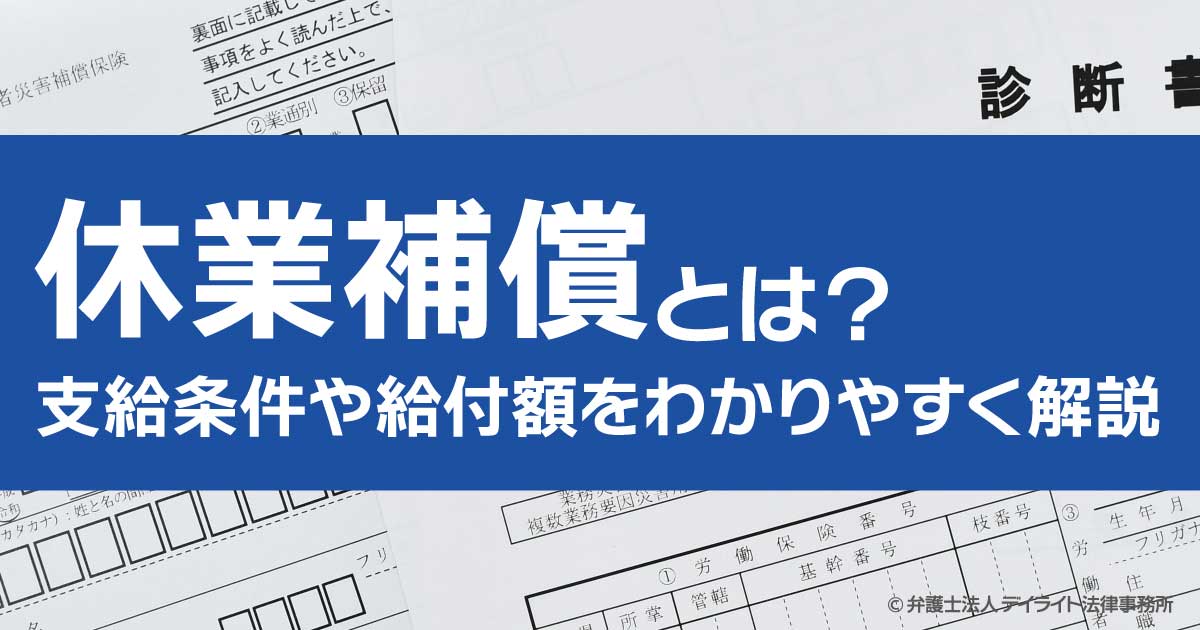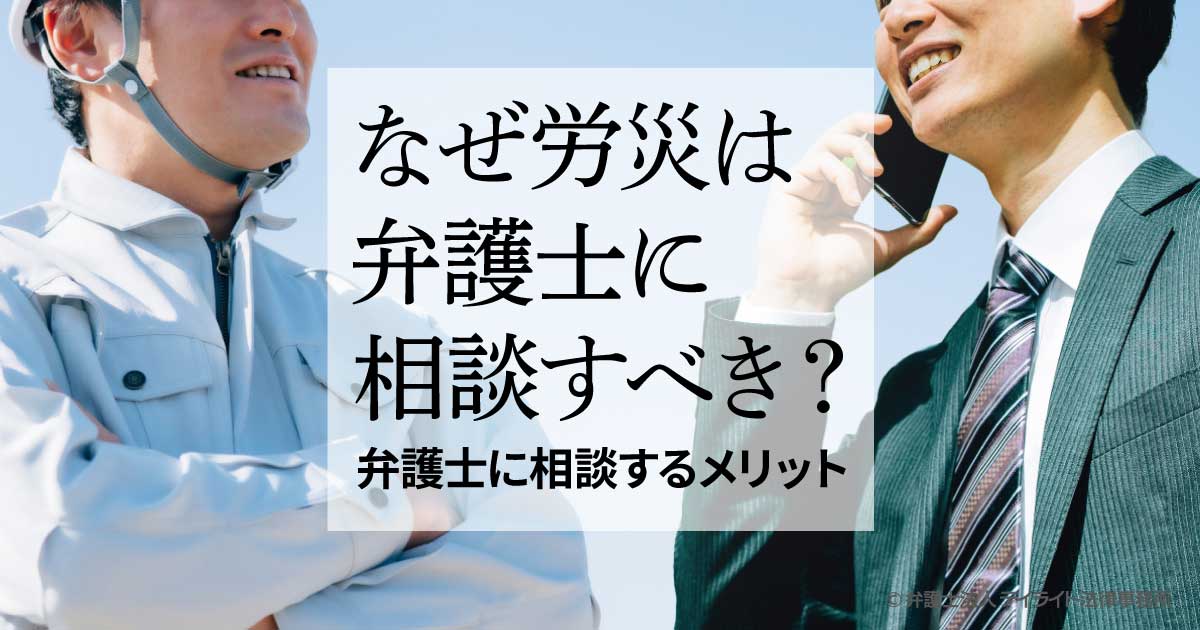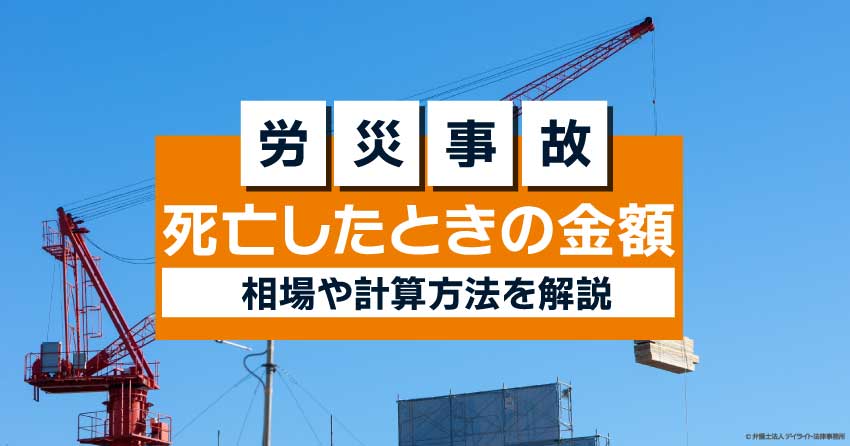
労災事故で死亡した場合には、労災保険からの給付金だけでなく、会社に対する損害賠償を請求することができる可能性があります。
労災死亡事故の損害賠償の金額は、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用などを合わせて、数百万円から数千万円、場合によっては1億円を超えます。
この損害賠償額をもとに、過失相殺、素因減額によって調整し、労災保険から受け取った給付金を損益相殺によって差し引いて、最終的な損害賠償の金額が算定されます。
会社に損害賠償を請求する際には、損害賠償の金額を算定する、労災保険から受け取れる金額についても確認する、会社の法的責任(安全配慮義務違反、不法行為など)や損害額に関する証拠を準備するなど、様々な対応が必要になります。
これらの事項に関する知識がないままに損害賠償を請求しても、示談交渉が難航したり、適切な損害賠償額を得られなかったりしてしまいます。
今回の記事では、労災事故で死亡した場合に請求できる損害賠償や労災保険の給付金の金額・計算方法、労災死亡事故の賠償金に関する注意点、損害賠償を請求する方法などについて解説していきます。
目次
労災事故で死亡した場合の金額の相場
労災死亡事故でもらえるお金の内容
労災事故で死亡した場合、遺族は次のようなお金を受け取ることができます。
- 損害賠償(会社の法的責任が認められる場合)
- 労災保険からの給付金(遺族補償給付、葬祭給付など)
これらのうち、損害賠償には、以下のような費目が含まれます。
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用 など
これらの損害賠償の費目ごとの金額の相場と、労災保険からの給付金の金額について見ていきましょう。
損害賠償の費目と各費目の金額の相場
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料は、従業員が労災事故によって死亡した場合に、死亡したことによる精神的苦痛への償いとして支払われるものです。
死亡慰謝料の相場は、死亡した従業員の家庭内での立場に応じて変わってきます。
死亡慰謝料の相場を表にすると、以下のようになります。
| ケース | 死亡慰謝料の相場 |
|---|---|
| 一家の支柱の場合
(*家庭の収入の大半を担っていた場合) |
2800万円 |
| 母親や配偶者の場合
(*収入の大半を担っているわけではなく、かつ、子育てや家事全般を担っていた場合) |
2500万円 |
| その他の場合
(*未婚の場合、幼児、子どもなど) |
2000万円~2500万円 |
以上のほかに、遺族自身の精神的な苦痛に対しても、別途慰謝料が認められることがあります(遺族固有の慰謝料)。
以下のページでは、労災の死亡事故が起こった場合の賠償金の相場、死亡事故が起こった場合に取るべき対応などについての解説を掲載しております。
死亡逸失利益の相場
死亡逸失利益とは、労災事故で死亡することがなければ得られたはずの収入のことです。
死亡逸失利益は、以下の計算式で計算します。
基礎収入 × (1-生活費控除率) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
上の式にある基礎収入は、事故前年の年収となります。
生活費控除率は、生きていれば必要となっていた生活費を損害賠償額から差し引くために用います。
生活費控除率の目安は、被害者の状況によって、以下のようになっています。
- 被害者が一家の支柱だった場合
(被扶養者が1名の場合)40% (被扶養者が2名以上の場合)30% - 被害者が女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 30%
- 被害者が男性(独身、幼児等を含む)の場合 50%
労働能力喪失期間は、死亡した時点から就労可能期間の終期とされている67歳までの期間です。
たとえば、45歳で亡くなった場合、労働能力喪失期間は、67 – 45 = 22年となります。
ライプニッツ係数は、逸失利益の計算で中間利息を控除するために用いられる係数です。
逸失利益は将来生じるはずだった利益を現時点で渡すものなので、本来利益が生じるはずだった時までの間に生じる利息を中間利息として控除する必要があるのです。
ライプニッツ係数には、中間利息の利率(法定利率)を年5%としたものと年3%としたものがあります。
令和2年4月1日より前の事故の場合は年5%、同日以降の事故の場合は年3%に対応するライプニッツ係数をそれぞれ用います。
死亡逸失利益の計算方法の具体例などについては、以下のページでもご紹介しています。
葬儀費用の相場
損害賠償で葬儀費用として認められる金額は、原則として150万円程度です。
実際の葬儀費用がこれを下回る場合は、実際に支出した額が損害賠償の対象となります。
一方、裁判例の中には、250万円までの葬祭費用を認めたものや、仏壇仏具の購入費、墓碑建立費、遺体搬送量、遺体処置費等についての損害賠償請求を認めたものもあります。
なお、香典については、受け取った額を損害賠償から差し引かれる(損益相殺される)ことはありません。
その一方で、香典返しは損害賠償の対象には含まれないこととなっています。
労災保険からの給付内容
死亡事故の場合、労災保険からは、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)と葬祭給付が支払われます。
ほかにも、亡くなる前に治療が行われている場合には、療養補償給付、休業補償給付などが給付されます。
ここでは、遺族補償給付の遺族補償年金、遺族補償一時金と葬祭給付の金額や支給を受けるための条件について見ていきます。
参考:遺族 補償 等給付 葬祭料等 葬祭給付 の請求手続|厚生労働省
遺族補償年金
労災保険から遺族補償年金が支給されるのは、労災によって従業員(被害者)が死亡した当時、被害者の収入によって生計を維持していた(共稼ぎも含む)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかがいる場合です。
ただし、妻以外の遺族については、被害者の死亡当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
これらの遺族がいる場合には、そのうちの最先順位者に遺族補償年金が給付されます。
参考:6-2 遺族(補償)等給付は誰が受給できますか。|厚生労働省
受給権者の順位は、以下のとおりです。
- ① 妻または60歳以上か一定障害の夫
- ② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
- ③ 60歳以上か一定障害の父母
- ④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- ⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母
- ⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
- ⑦ 55歳以上60歳未満の夫
- ⑧ 55歳以上60歳未満の父母
- ⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
- ⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
遺族補償年金を受け取ることができる場合には、遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の3つが支給されます。
これらの金額は、以下の表のとおりです。
| 遺族の数 | 遺族補償年金 | 遺族特別支給金(一時金) | 遺族特別年金 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 | |
| 注 *給付基礎日額は、原則として、事故の直前3か月間の給料の合計額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った金額です。*算定基礎日額は、事故の日以前1年間の特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金。臨時に支払われた賃金は含まない。)の総額を算定基礎年額として、これを365で割った金額です。ただし、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(150万円が上限額)。*受給権者が2人以上あるときは、上の額を等分してそれぞれの受給権者が受け取ります。 |
|||
なお、遺族補償年金を受給することになった遺族は、一回に限り、年金の前払いを受けることができます(遺族補償年金前払一時金)。
遺族補償年金については、以下のページもご参照ください。
遺族補償一時金
遺族補償一時金が給付されるのは、以下のいずれかの場合です。
- ① 従業員が死亡した当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合
- ② 遺族補償年金の受給権者が最後順位者まで全て失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たないとき
遺族補償一時金の受給権者は、以下のとおりです。
- ① 配偶者
- ② 従業員の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父
- ③ その他の子・父母・孫・祖父母
- ④ 兄弟姉妹
- ⑤ 内容
①から順に先順位者となり(②、③の中では、子・父母・孫・祖父母の順)、同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。
遺族補償一時金の金額は、以下のとおりとなっています。
| 条件 | 給付内容 |
|---|---|
| ① 従業員が死亡した当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合 |
|
| ② 遺族補償年金の受給権者が最後順位者まで全て失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
|
葬祭給付
葬祭給付は、労働者が労災で死亡した場合に、葬儀費用を補償するものです。
葬祭給付を受け取ることができるのは、葬儀を行う者となります。
「葬儀を行う者」は通常は遺族ですが、葬儀を行う遺族がおらず会社が社葬を行った場合は、会社に対して葬祭給付が支給されます。
葬祭給付の金額は、以下のいずれか高い方になります。
②①の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分
労災死亡事故の賠償金の計算方法
労災死亡事故の賠償金は、生じた損害の費目ごとの金額を合算して計算します。
具体例で見てみましょう。

死亡する前に治療を受けていた場合には、その間に発生した入院雑費、付添費用、休業損害、入通院慰謝料などについても損害賠償請求することができます。
なお、治療費については、労災の場合、労災保険からの療養補償給付で全額カバーされますので、損害賠償に含めることはできません。
労災死亡事故の注意点
労災保険でもらえるお金は一部でしかない
労災で死亡した場合、上でもみたとおり、労災保険から遺族補償給付などが給付されます。
しかし、労災保険からの給付では、労災による損害の一部しか補償されません。
たとえば、慰謝料は、労災保険からは支給がなく、会社に損害賠償として請求しなければ補償されません。
また、労災によるケガの治療・療養のために仕事を休んだことで生じた減収については、労災保険では休業補償で、損害賠償では休業損害で補償されることになります。
しかし、休業補償は、休業開始後4日目からしか対象となりませんし、金額も給付基礎日額の60%(休業特別支給金を合わせても80%)までしか支払われませんので、残りについては損害賠償(休業損害)として請求する必要があります。
逸失利益についても、遺族補償給付では足りない分については、損害賠償でカバーすることになります。
慰謝料等を会社に請求するには証拠が必要
労災認定を受けることができたからといって、必ず会社に対する損害賠償請求が認められるとは限りません。
会社に損害賠償を請求するためには、会社に労災事故に対する法的責任(安全配慮義務違反、不法行為など)が認められる必要があります。
この法的責任が会社にあること(会社に安全配慮義務に違反する行為や過失に当たる行為があったことなど)は、遺族の側で立証する必要があります。
また、事故によって生じた損害やその金額についても、遺族の側で立証する必要があります。
そのため、会社に労災の損害賠償を請求する際には、会社の法的責任や事故による損害についての証拠を準備しておくことが重要になります。
過失相殺や素因減額を主張される可能性がある
労災の損害賠償を請求すると、会社側から「従業員にも過失があった」「従業員が元から有している要因(素因)が被害を拡大させた」などとして、過失相殺や素因減額による損害賠償額の減額を主張される可能性があります。
こうした会社の主張に有効に反論できないと、損害賠償の額が減額されてしまうおそれがあります。
労災の損害賠償を請求する際には、会社から過失相殺や素因減額などの主張が出される可能性も考えて、あらかじめ、死亡した従業員には過失などがなかったことを裏付ける資料など、自身にとって有利な証拠を準備しておけるとよいです。
労災死亡事故で会社に損害賠償請求する方法
損害賠償請求の流れ
労災事故で死亡した場合の損害賠償請求の流れは、以下の図のようになります。
労災申請
労災による死亡事故の場合、示談交渉に先立って労災申請を行うのが一般的です。
労災申請は、従業員側で行うこともありますし、会社が代行して行うこともあります。
労災申請をするには大量の申請書や資料が必要となりますので、この段階から弁護士のサポートを受けることも検討することをお勧めします。
損害賠償責任の有無の検討
労災の損害賠償を請求する前に、会社に損害賠償責任(安全配慮義務違反、不法行為責任など)を問えるかどうか(損害賠償責任の有無)を検討する必要があります。
そのためには、事故状況や業務の手順、作業環境などについて調査し、資料を収集する必要があります。
損害賠償額の算定
会社に損害賠償責任があると考えられるのであれば、損害賠償額を算定します。
損害賠償額を誤って算定すると、示談交渉が難航したり、適切な賠償金額を得られなかったりしてしまいます。
損害賠償額の算定については、ご自身で算定してみた場合であっても、一度労災に強い弁護士に相談し、確認してもらうことをお勧めします。
示談交渉~示談成立
損害賠償額の算定ができたら、示談交渉を開始します。
示談交渉は、労災保険からの給付が確定し、損害賠償から控除しなければならない額が決まってから始めるのが一般的です。
示談交渉では、損害賠償責任の有無、賠償の対象となる損害の範囲、賠償金額、支払時期や支払方法、過失相殺・素因減額の有無・程度などについて話し合われます。
労使間で合意が成立すれば、示談成立となります。
示談成立に当たっては、示談書が作成されるのが一般的です。
示談書にサインをしてしまうと、後から内容を変更することは大変難しくなります。
示談書にサインをする前には、一度弁護士に相談し、内容が適切かどうかを確認してもらいましょう。
労災の示談については、以下のページもご覧ください。
示談不成立~訴訟・労働審判
示談交渉をしても合意できない場合には、示談不成立となります。
その場合には、訴訟や労働審判を提起して損害賠償の支払を求めていくことになります。
訴訟も労働審判も、裁判所に提起することになります。
損害賠償請求で必要となるもの
損害賠償請求の際には、次のことを立証できる資料を揃えておくことが大切です。
- 会社に法的責任(安全配慮義務違反、不法行為など)があること
例:労働基準監督署が作成する事故の調査復命書
警察が作成する事故の実況見分調書
作業手順のマニュアル
機器の使用説明書
職場の関係者・元従業員などの陳述書
本人や家族の日記・手記など - 労災によって被害者が死亡したこと(戸籍謄本、死亡診断書など)
- 損害額(源泉徴収票、給与明細、葬儀費用の領収証など)
- 労災保険からの受給金額がわかるもの(労災保険給付の支給決定通知、支払振込通知)
労災死亡事故で賠償金を請求するポイント
死亡慰謝料は全額が損害賠償の対象になる
死亡慰謝料は、労災保険ではカバーされていないため、労災保険からの給付金を損益相殺で差し引かれることはなく、全額会社に請求することができます(過失相殺や素因減額での減額はあります)。
損害賠償について過失相殺などが行われたために、遺族補償給付の額が死亡逸失利益の額を上回ったとしても、その上回った額を慰謝料など他の賠償金の費目から差し引くことはできません。
損益相殺については、以下のページもご参照ください。
会社からの提案は慎重に検討する
会社から示談案を提示された場合には、その内容が適切なものかどうかを慎重に検討する必要があります。
- 損害額が低く見積もられていないか
- 過失相殺や素因減額が行われていないか
- 損益相殺の対象とならない遺族特別支給金や遺族特別年金、遺族特別一時金が控除されていないか
- 死亡慰謝料から労災保険の給付金が差し引かれていないか
- 会社から支払われた見舞金や上積補償はどのように取り扱われているか
など、様々な点についての確認が必要です。
確認漏れが起こらないようにするためにも、会社からの示談案を受け取ったら、一度労災に強い弁護士に相談し、内容を確認してもらうことをお勧めします。
労災に強い弁護士に相談する
労災死亡事故について損害賠償や労災保険を請求する場合、ご遺族のその後の生活を守るためにも、適正な金額を獲得できることが大変重要です。
そのため、労災死亡事故で賠償金や労災保険を請求する場合は、なるべく早いうちから、労災に強い弁護士に相談することをお勧めします。
労災に強い弁護士に相談・依頼することには、以下のようなメリットがあります。
- 労災の損害賠償責任に関する資料収集をしてくれる
- 会社や労基署との対応を任せることができる
- 適切な損害賠償額を獲得できるように示談交渉や裁判を進めてくれる
- 労災認定や後遺障害等級認定についてもサポートしてくれる
- わからないこと、心配なことについて、その都度聞くことができる
労災の損害賠償を請求される会社側も、適切に示談交渉を進めるためには労災に強い弁護士に相談することが大切です。
労災に強い弁護士に依頼することのメリットについては、以下のページでもご紹介しています。
労災死亡事故と賠償金のQ&A

なぜ労災は弁護士に相談すべき?弁護士に相談するメリット
 労災死亡事故を起こした場合に会社に生じうるデメリットとしては、次のようなものがあります。
労災死亡事故を起こした場合に会社に生じうるデメリットとしては、次のようなものがあります。- 多額の損害賠償を支払わなければならなくなる
- 死亡した従業員の遺族から裁判を起こされる
- 労災保険料が上がる
- 労働基準監督署への報告や調査への立会いが必要になり、時間がとられる
- 会社の企業イメージがダウンする
- 取引先から取引を打ち切られる
- 多数の従業員が退職する
- 求人への応募が激減し、採用が難しくなる
- 刑事罰などを受けるリスクが生じる
労災を起こしたことによって会社が受けるダメージについては、以下のページもご覧ください。

労災死亡事故で遺族は年金を受け取れる?
 労災死亡事故の場合、一定の条件を満たせば、遺族は遺族補償年金を受け取ることができます。
労災死亡事故の場合、一定の条件を満たせば、遺族は遺族補償年金を受け取ることができます。遺族補償年金を受け取れる遺族は、以下の条件を満たす方になります。
- 従業員が死亡した当時、死亡した従業員の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のいずれかである
- 妻以外の場合、従業員が死亡した当時に一定の高齢又は年少であるか、又は一定の障害の状態にあった
まとめ
今回は、労災事故で被害者が死亡した場合に請求できる損害賠償と労災保険の金額、損害賠償の請求方法、損害賠償を請求する際の注意点などについて解説しました。
労災保険や労災の損害賠償の請求を適切に行うには、専門的な知識や経験も必要になりますので、早いうちから労災に強い弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。
デイライト法律事務所では、多数の労災事故事件に対応してきた労働事件チームの弁護士が、労災死亡事故についてのご相談をお受けしております。
従業員の方からも、会社側からも、ご相談をお受けしております。
電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応可能です。
労災の慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。