
 労働災害が発生した場合に、企業が民事上の責任を負うのはどのような場合ですか?また、どういった費目の賠償をしなければならないのでしょうか?
労働災害が発生した場合に、企業が民事上の責任を負うのはどのような場合ですか?また、どういった費目の賠償をしなければならないのでしょうか?

 労働災害が発生したことについて、企業に安全配慮義務違反が認められる場合には、企業は民事上の責任を負うことになります。
労働災害が発生したことについて、企業に安全配慮義務違反が認められる場合には、企業は民事上の責任を負うことになります。
補償内容は、治療費、慰謝料、逸失利益など、労働災害による負傷と因果関係のある損害を補償しなければなりません。
企業の民事上の責任
 業務災害が発生した原因が労働基準法や労働安全衛生法に違反しているような場合には、企業及び代表者や現場監督者などは刑事上の責任を追及される可能性があります。
業務災害が発生した原因が労働基準法や労働安全衛生法に違反しているような場合には、企業及び代表者や現場監督者などは刑事上の責任を追及される可能性があります。
また、業務災害の原因として、企業の安全配慮義務違反が認められる場合には、企業は労働者に対して民事上の損害賠償責任を負うことになります。
業務災害の場合には、労災保険が使用できるので、一定額については労災保険で補償することができますが、労災保険を超える部分に関しては、企業が労働者に補償しなければなりません。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、使用者が支配管理下にある労働者の安全と健康を守らなければならない義務のことです。
 この点、最高裁判所は、自衛隊八戸工場事件(最判昭50.2.25民集29巻2号143頁)において安全配慮義務について以下のように述べています。
この点、最高裁判所は、自衛隊八戸工場事件(最判昭50.2.25民集29巻2号143頁)において安全配慮義務について以下のように述べています。
「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである。」
「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠…(以下省略)」と判示しています。
この事例は、国と公務員に関する判例ですが、安全配慮義務が「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」と考えるならば、民間の場合においても使用者と労働者の間には同様の義務が存在すると考えられることになります。
 さらに、川義事件(最三小判昭59.4.10民集38巻6号557頁)では、
さらに、川義事件(最三小判昭59.4.10民集38巻6号557頁)では、
「雇用契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。」と判示しています。
この事例は、宿直中の労働者が強盗に刺殺された事故であるが、安全配慮義務の具体的な内容として強盗侵入防止の物的設備を十分に施し、かつ宿直員の安全教育を行う等の義務があったと判示しています。
このように、使用者が労働者に対して安全配慮義務を負っていることは多くの裁判例により確立されています。
安全配慮義務を負う主体
労働者の直接の雇用主が、労働者に対して安全配慮義務を負うことは当然ですが、直接の雇用主でない場合でも安全配慮義務を負う場合があります。
例えば、最高裁判所は、元請事業主と下請労働者との安全配慮義務について、元請事業主の管理する設備、工具などを用いて、元請事業主の指揮、監督を受けて稼働しており、元請事業主の労働者とほとんど同じ作業内容であった事案で元請事業主が下請事業主の労働者に対して安全配慮義務を負うと判示しています(三菱難聴訴訟事件 最一小判平3.4.11労判590号14頁)。
また、親会社と子会社の労働者との関係について、以下のように親会社に安全配慮義務があることを認めた裁判例(長野じん肺訴訟 長野地判昭61.6.27判時1198号3頁)があります。
「親会社、子会社の支配従属関係を媒介として、事実上、親会社から労務提供の場所、設備、器具類の提供を受け、かつ親会社から直接指揮監督を受け、子会社が組織的、外形的に親会社の一部門の如き密接な関係を有し、子会社の業務については両者が共同してその安全管理に当り、子会社の労働者の安全確保のためには親会社の協力及び指揮監督が不可欠と考えられ、実質上子会社の被用者たる労働者と親会社との間に、使用者、被用者の関係と同視しできるような経済的、社会的関係が認められる場合には、親会社は子会社の被用者たる労働者に対しても信義則上右労働関係の付随義務として子会社の安全配慮義務と同一内容の義務を負担するものというべきである。」と判示しています。
 このように、直接の雇用関係がなかったとしても、安全配慮義務を負う場合がありますので、使用者としては、自社の支配管理下にある労働者に対しては、その労働者の安全・健康について注意を払わなくてはいけません。
このように、直接の雇用関係がなかったとしても、安全配慮義務を負う場合がありますので、使用者としては、自社の支配管理下にある労働者に対しては、その労働者の安全・健康について注意を払わなくてはいけません。
安全配慮義務の履行
安全配慮義務の内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的状況によって内容が異なりますが、一つの基準となるのが、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則等の安全衛生関係の法令です。
労働基準法に満たない労働条件は無効とされており(労基法13条)、さらに、労働基準法42条では「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる。」と規定されていますので、労働安全衛生法に違反する労働条件は無効ということになります。
すなわち、労働安全衛生法の安全衛生基準は最低労働条件となるのです。
労働安全衛生規則では、「第二編 安全基準」の項目があり、その中で具体的な安全基準が規定されています。
 企業は、安全配慮義務を果たし労働災害を防止するには、自社の業務に関連する法令に関して十分に把握しその安全基準を満たさなければなりません。リスクアセスメントを実施し、職場の潜在的な危険性又は有害性を洗い出し、リスクの排除・低減措置を講じていかなければなりません。
企業は、安全配慮義務を果たし労働災害を防止するには、自社の業務に関連する法令に関して十分に把握しその安全基準を満たさなければなりません。リスクアセスメントを実施し、職場の潜在的な危険性又は有害性を洗い出し、リスクの排除・低減措置を講じていかなければなりません。
賠償内容
企業に安全配慮義務違反が認められ、民事上の賠償責任が認められた場合には、被災労働者に生じた損害の賠償をしなければなりません。主な賠償項目は以下のとおりです。
主な賠償項目
 〇治療費
〇治療費
〇付添費用
〇将来介護費
〇通院交通費
〇家屋・自動車等改造費
〇葬儀関係費用
〇休業損害
〇慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)
〇後遺障害・死亡逸失利益など
上記の損害項目の中で高額になりがちなのが、逸失利益です。逸失利益とは、被災しなければ、本来得ることができたであろう利益のことです。
後遺障害に該当した場合には、それだけ働きづらくなっているわけですから、等級に応じた労働能力の喪失率が認められることになります。年収額や年齢に応じて計算されることになります。
下記の事例は、逸失利益算定の一例です。片目を失明した場合には、後遺障害等級8級1号「一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの」に該当します。
労働能力喪失期間は67歳までの27年間で計算され、中間利息を控除するための係数であるライプニッツ係数を使用して計算されます。
下記の事例をみても分かるように、逸失利益は、将来において支払うべきものを一時金として支払うことになるため、高額になりがちです。資金力に乏しい中小企業に関しては、保険を利用する等してリスクヘッジすることが大切です。
逸失利益の計算例
≪事例≫
40歳男性、会社員(年収500万円)が、建設工具を製作する事業場で、作業中に片目を失明した場合。
〇後遺障害等級
8級1号
〇労働能力喪失率
45%(8級相当)
〇労働能力喪失期間
27年(ライプニッツ係数14.6430)
(計算式)
500万円×0.45×14.6430=3294万6750円
逸失利益の賠償額 ⇒ 3294万6750円
参考裁判例
シルバー人材センターの安全配慮義務
【判例】綾瀬市シルバー人材センター事件(横浜地判平15.5.13判時1825号141頁)
 (事案の概要)
(事案の概要)
Xは、退職後、Yシルバー派遣センターに登録して自動車部品などを製造する業務に従事していた。業務内容は、プレスブレーキという鉄板を折り曲げる機械を使用して鉄板を折り曲げる作業をしていた。
このプレスブレーキは、作業員が鉄板をテーブル奥のストッパーに合わせてテーブルに載せてから、手を離し足(右足)でフットスイッチを踏み込んでラムを下降させることによりラムの強い圧力で鉄板を折り曲げる仕組みとなっていた。
Xは工場長から実演を含めて指導を受けた上で作業を開始し、1時間ほど作業を行ったところ、鉄板の左側がテーブル奥のストッパーの下に入ってしまったため、これを引き出して正しい位置に戻そうとして左手をテーブルとラムの間に差し入れた。
原告は、その際、誤ってフットスイッチを踏み込んでラムを下降させてしまい、左手4指をその基節骨基部から切断してしまった。
XはYセンターにに安全配慮義務違反があったとして損害賠償請求をした。
(判旨の概要)
「高齢者事業団、シルバー人材センター、ひいてはYセンターの設立の経緯、高年齢者雇用安定法の成立及び関係規定の内容、労働省の行政指導の内容、Yセンター設立前後の綾瀬市ないし事業団の広報活動の内容、Yセンターにおける就業の機会の確保及び提供の仕組み、一般に指摘されている加齢によって人が持つに至る身体的心理的特性などの認定事実に、「事業団は、健康で働く意欲を持つ高齢者…の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、高齢者の生きがいの充実と社会参加の促進を図るとともに、その経験と能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。」(規約3条)とのYセンターの目的を合わせ考えれば、Yセンターは、規約4条1号に基づいて高齢者である会員に対して就業の機会を提供するに当たっては、社会通念上当該高齢者の健康(生命身体の安全)を害する危険性が高いと認められる作業を内容とする仕事の提供を避止し、もって当該高齢者の健康を保護すべき信義則上の保護義務(健康保護義務)を負っているものと解するのが相当である。」と判示した上で、「本件プレスブレーキによる作業は、作業内容等の客観的事情とXの年齢、職歴等の主観的事情とを対比検討した場合、社会通念上高齢者である原告の健康を害する危険性が高いと認められる作業に当たるということができる。にもかかわらず、Yセンターは、本件プレスブレーキによる作業も含まれるものとしてXに対して上記工場内作業の仕事を提供し、Xがこれに応じて本件プレスブレーキによる作業に従事した結果、本件事故に至ったのであるから、Yセンターは、Xに対する健康保護義務の違背があったものとして、債務不履行に基づき、本件事故によってXが被った損害を賠償すべき義務があるというべきである。」
(判例のポイント)
本事件では、YシルバーセンターはXを直接指揮監督下において就労させていたわけではありません。
しかし、シルバー人材センターなどの事業団が設立された経緯や、Yセンターの目的などから、Yセンターは就業の機会を提供するにあたって、当該高齢者の健康を保護するという健康保護義務があると認定しています。
その上で、本件ではプレスブレーキを使用した危険な業務が含まれているにもかかわらず、仕事の提供をした結果、事故が発生したとしてYセンターに賠償責任を認めているのです。
本件のように、直接の指揮命令下にない場合であっても、安全配慮義務違反を問われることがありますので、企業としては、自社の業務の特性を十分に把握し、労働災害の発生を防止するよう工夫しなければなりません。
いじめによる自殺が安全配慮義務違反とされた事例
【裁判例】川崎水道局事件(横浜地川崎支判平14.6.27判時1805号105頁、労判833号61頁)
 (事案の概要)
(事案の概要)
Xはもともと内気な性格であったが、勤務評定はよかった。しかし、配転があり、Xは、新たな課に配属されたところ、上司である課長Y1、係長Y2、主査Y3ら3人が、嫌がらせの言動を繰り返すようになった。
Xは、胃痛、食後に吐き気の症状が出るようになり、同症状は心因反応であると医師に診断された。また、B課長は、Xがいじめを訴えたものの、十分な調査を実施しなかった。その後、Xは統合失調症と診断され、欠勤が多くなり自殺するに至った。
(判示の概要)
「市は市職員の管理者立場に立ち、そのような地位にあるものとして、職務行為から生じる一切の危険から職員を保護すべき責務を負うものというべきである。そして、職員の安全の確保のためには、職務行為それ自体についてのみならず、これと関連して、ほかの職員からもたらされる生命、身体等に対する危険についても、市は、具体的状況下で、加害行為を防止するとともに、生命、身体等への危険から被害職員の安全を確保して被害発生を防止し、職場における事故を防止すべき注意義務(以下「安全配慮義務」という。)があると解される。」と判示した上で、「このような経過及び関係者の地位・職務内容に照らすと、工業用水課の責任者であるY1は、Y2などによるいじめを制止するとともに、Xに自ら謝罪し、Y2らにも謝罪させるなどしてその精神的負荷を和らげるなどの適切な処置をとり、また、職員課に報告して指導を受けるべきであったにもかかわらず、Y2及びY3によるいじめなどを制止しないばかりか、これに同調していたものであり、B課長から調査を命じられても、いじめの事実がなかった旨報告し、これを否定する態度をとり続けていたものであり、Xに自ら謝罪することも、Y2らに謝罪させることもしなかった。また、Xの訴えを聞いたB課長は、直ちに、いじめの事実の有無を積極的に調査し、速やかに善後策(防止策、加害者等関係者に対する適切な措置、Xの配転など)を講じるべきであったのに、これを怠り、いじめを防止するための職場環境の調整をしないまま、Xの職場復帰のみを図ったものであり、その結果、不安感の大きかったXは復帰できないまま、症状が重くなり、自殺に至ったものである。したがって、Y1及びB課長においては、Xに対する安全配慮義務を怠ったものというべきである。」
(裁判例のポイント)
裁判例では、Y1、Y2、Y3のいじめの事実が認定され、また、いじめの事実について十分な事実調査を実施せず、Xの配転を実施するなど、いじめを防止するための適切な処置を実施しなかったとして、B課長、Y1の安全配慮義務違反を認めています。
結果論にはなりますが、B課長がいじめの事実を認識しえた時点で厳正な事実調査を実施し、迅速にしかるべき措置を講じていれば、Xの自殺を防止できていたかもしれません。企業が行う事実調査においては、仲間意識からか十分な調査や措置が講じられないことがありがちです。
企業内でこうした悲劇を起こさないためにも公正中立な調査を実施し、迅速に適切な措置を講じなければなりません。
なお、本件では、X自身の心因的要因も加わって自殺の契機となったとして、過失相殺の規定を類推適用し、損害額の7割減額されています。
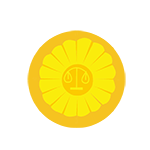 労働災害が発生した場合には、企業は多額の補償をしなければならないケースもあります。労働災害が発生しお困りの経営者の方は、お気軽にご相談ください。企業側に立った労働問題を数多く扱う弁護士が対応させて頂きます。
労働災害が発生した場合には、企業は多額の補償をしなければならないケースもあります。労働災害が発生しお困りの経営者の方は、お気軽にご相談ください。企業側に立った労働問題を数多く扱う弁護士が対応させて頂きます。


