親権は何歳まで有効?影響はある?弁護士が解説
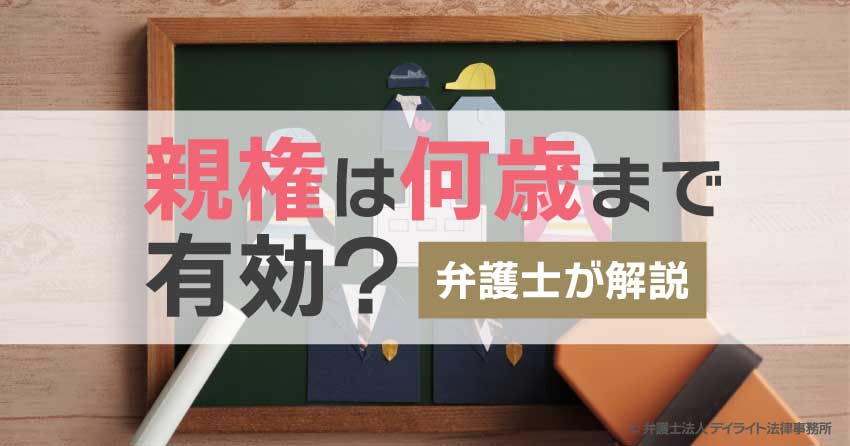
親権は、子どもが18歳になるまで有効です。
法律では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められています。
成人年齢は、かつては20歳でしたが、法改正により18歳に引き下げられました。
したがって、親権を行使することができるのは、子どもが18歳に達するまでであり、18歳に達したら親権は消滅します。
しかし、法改正後も、養育費の終期は、引き続き20歳が原則となります。
ここでは、親権をいつまで行使できるのかについて、親権がなくなることの影響、成人年齢の引き下げによる影響などもあわせて解説していきます。
親権を行使できるのはいつまで?

親権を行使できるのは、子どもが満18歳になるまで(18歳の誕生日を迎えるまで)です。
民法では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と規定されています(民法818条1項)。
成年年齢は現行の民法では18歳と定められているため(民法4条)、親権に服するのは18歳未満の子どもということになります。
したがって、親権を行使できるのは子どもが18歳になるまでであり、子どもが18歳に達したら親権は消滅します。
なお、以前は成年年齢は20歳とされていましたが、法律の改正により18歳に引き下げられました。
改正法は2022年4月1日から施行されています。
親権とは?
親権とは、簡単に言うと、子どもの身の回りの世話をしたり、子どもの財産を管理したりするため、その父母に認められる権利や義務のことをいいます。
親権には、大きく分けて次の2つの内容があります。
- ① 子の身上に関する権利義務(身上監護権)
- ② 子の財産についての権利義務(財産管理権)
①身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をして子どもを育てるための権利義務のことをいいます。
身上監護権には次のような権利義務が含まれます。
| 監護教育権 | 子どもの監護(身体的な育成を図ること)と教育(精神的な発達を図ること)をする権利義務(民法820条) |
|---|---|
| 居所指定権 | 子どもの住む場所を決める権利義務(民法822条) |
| 職業許可権 | 子どもの職業を許可、取消、制限する権利義務(民法823条) |
②財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利義務、及び子どもの財産に関する法律行為(契約など)を代理で行う権利義務(法定代理権)のことをいいます(民法824条)。
なお、財産に関するものではない行為(「身分行為」といいます。)については、民法上に明文規定がある場合(例えば、15歳未満の子の養子縁組の代諾(民法797条1項))に限って親権者が代理で行うことができます。
成人年齢引き下げによる影響
なぜ成人年齢が引き下げられたのか?
先ほども述べたように、成人に達する年齢は、法改正により20歳から18歳に引き下げられました。
憲法改正の国民投票権年齢や選挙権年齢等が18歳に引き下げられたことや、世界的には成人年齢を18歳とするのが主流ということを踏まえ、このような引き下げがされることになりました。
法改正の影響とは?
子どもが18歳に達すると親権は消滅する
法改正前は、18歳、19歳の子どもも親権に服していましたが、法改正により、18歳、19歳の子どもは親権に服さなくなりました。
子どもが18歳に達すると親権は消滅します。
子どもが18歳に達すれば、親の身上監護権(監護教育権、居所指定権、職業許可権)は消滅します。
そのため、18歳に達した子どもは、自分の意思で進路や就職先、住む場所を自由に決められるようになります。
もっとも、18歳に達しても、引き続き親による経済的な支えが必要になるケースは多いです。
例えば、大学や専門学校へ進学し、学費や一人暮らしのための家賃などを親に負担してもらう場合もありますし、引き続き親元で暮らして住居費や食費などを親に頼っているという場合もあります。
このような場合、事実上は、進学先や居住先の決定に親の承諾が必要となるでしょう。そのため少なくとも子どもが経済的に自立するまでの間は、親権がなくなっても、事実上の親の影響力はそれまでとは変わらないというケースは少なくないでしょう。
しかし、これはあくまでも事実上のことであり法律上は、親が子どもの進学先や居住先を決定する権利義務はなくなります。
また、親権が消滅すれば、父母の共同親権者としての関係もなくなりますから、父母が子どもの進路や居住場所などについて話し合って決める必要などもなくなります。
子どもが18歳に達すれば、子どもは、自分の財産を自分自身で管理するようになります。
また、子どもの財産に関する法律行為は、子ども自身が一人で有効に行うことができるようになります。
親権者だった者は、子どもが18歳に達したら、これまで管理していた子どもの財産の収支を速やかに計算しなければならないとされています(民法828条本文)。
参考:民法|e-Gov法令検索
そして、子どもの財産を管理する権利を失うことに伴い、これまで管理していた子どもの財産を子どもに渡す必要があります。
例えば、親が子ども名義の預金口座を作り、そこに祖父母からの誕生祝・入学祝やお年玉などを入金していた場合、その口座の通帳等を子どもに渡して以後は子どもに自分自身で管理してもらうことになります。
なお、子ども名義の預金口座に親のお金を入金している場合は、子どもに当該預金口座を渡す際、親のお金を子どもに渡したものとみなされ、金額やお金の使い道によっては贈与税がかかることがあります。
心配な場合は、税務に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。
18歳になれば子どもが一人で有効な契約ができるようになる
法改正前は、18歳、19歳の子どもは「未成年」であったため、契約などの法律行為をするには法定代理人の同意が必要となるのが原則で、同意なく行われた行為については取り消すことができました(民法5条1項2項参照)。
参考:民法|e-Gov法令検索
親権に服する子どもの法定代理人は親権者ですから、かつては、18歳、19歳の子どもは親権者の同意なく一人で契約等をすることはできなかったということです。
それが法改正で成年年齢が引き下げられたことにより、18歳、19歳の子どもも、親の同意なく一人で有効な契約等をすることができるようになりました。
したがって、例えば、携帯電話の契約、一人暮らしのための賃貸借契約、ローン契約なども18歳、19歳の子どもが一人ですることができます。
そして、これらの契約をした後に、18歳、19歳であることを理由に取り消すことはできなくなりました。
なお、子どもが18歳に達しても、精神上の障害などにより、自分自身で財産管理をしたり、法律行為をしたりすることが難しい場合があります。
そのような場合でも、当然に親が子どもの財産を管理したり、法律行為を代理で行えるわけではありません。
財産管理等についてサポートが必要な場合は、成年後見等の開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立ての結果、成年後見人等として親が選任された場合は、子どもが18歳に達した後も、引き続き親が子どもの財産を管理したり、必要な場合は子ども自身が行った法律行為を取り消したりすることになります。
(なお、選任は裁判所が行いますので、必ず親が選任されるとは限りません。)
ただし、これはあくまでも成年後見人等の職務として行われるものであり、親権者の財産管理権とは全くの別物となります。
親権の消滅と養育費の関係

法改正は、養育費の終期(いつまで支払うか)に基本的には影響を及ぼしません。
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立可能になるまでにかかる生活費、医療費、教育費などの費用のことをいいます。
養育費は、通常、離婚後に子どもと離れて暮らす親(非監護親)が子どもと一緒に暮らす親に対し、毎月一定額を支払うという形で支払いが行われます。
法改正以前は、養育費の終期については「子どもが成人に達するまで(又は成人に達する日の属する月まで)」との定めがされる場合が多数でした。
そのため、法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、養育費の終期も原則18歳になるのかが問題となります。
この点、養育費の終期は、抽象的には「子どもが未成熟子でなくなるまで」とされています。
「未成熟子」とは、自分の労力や資産で生計を立てることができない者のことをいいます。
すなわち、養育費の終期は、「子どもが独立して自分で生計を立てることができるようになるまで」ということになります。
未成熟子でなくなるのと、成人年齢に達するのは必ずしもイコールではありません。
もっとも、社会状況として、20歳に達すれば独立可能になるというのが一般的であるため、養育費の終期は原則20歳(=以前の成人年齢)までとされていました。
そして、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられても、このような社会状況は変わりません。
そのため、法改正後も、養育費の終期は、引き続き20歳が原則となります。
ただし、20歳までというのはあくまでも原則であり、具体的に何歳まで支払うことになるかは状況次第です。
例えば、子どもが大学生の場合は大学卒業まで(「22歳に達した後の3月まで」など)支払義務を負うとされることもありますし、18歳で就職して自活した場合は就職した月までで支払い終了となることもあります。
親権と年齢に関するQ&A
![]()
親権は、何歳まで母親が有利ですか?
離婚後に単独親権となるケースで、親権者を母親とするか、父親とするかで争いになった場合は、子どもの年齢が小さいほど母親の方が有利になる傾向にあります。
筆者の個人的な感覚としては、子どもが小学生の間くらいまでは、母親の方が有利になるケースが多いです。
単独親権の場合に、父母のどちらが親権を取るかについては、どちらを親権者とするのが子どもの利益になるかという観点から決められることになります。
その際には、監護の継続性の原則が重視される傾向にあります。
これは、子どもの養育者を変えると子どもへの心理的不安定をもたらす恐れがあるため、現在の監護状況に問題がない限りは、現実の監護者を優先させるべきという考え方です。
この考え方に基づくと、これまで主として子どもの世話をしてきた側(主たる監護者)の方が有利になります。
そして、主として子どもの世話をしているのは母親というケースは多いです。
特に、子どもが小学生くらいまでは、母親が専業主婦として、あるいは時短やパートタイムで働きながら育児を担当しているという家庭が多い傾向にあります。
母親が無条件で優先されるということでは決してありませんが、以上のような社会の状況から、子どもの年齢が小さいほど母親が有利になる傾向にあるのが現状です。
![]()
子供が親権者を選べる年齢とは?
親権者は父母間の協議又は裁判所の判断によって決めるものであり、子どもが自由に選べるものというわけではありません。
もっとも、子どもの意思は親権者を決める際に考慮され、状況によっては重要視されます。
裁判所が決める場合は、子どもが15歳以上のときは、必ず子どもの陳述(意見)を聴かなければならないものとされています(家事事件手続法169条2項)。
15歳に達していれば精神的に成熟し、大人と同様に扱ってよいといえる場合がほとんどです。
そのため、特段の事情がない限りは、子どもの意思に反した結論になることはありません。
したがって、子どもの意思が唯一の判断基準というわけではありませんが、子どもが15歳以上の場合は子どもの意思が決定的な要素となることがほとんどといってよいでしょう。
また、子どもが15歳未満の場合でも、裁判所は、子どもの意思を把握するように努め、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないものとされています(同法258条1項・65条)。
実務では、子どもが10歳くらいに達している場合は、子どもの意思が確認される運用がされています。
個人差はあるものの、そのくらいの年齢に達している場合は、自分の意思を表明できる能力に問題はないとされ、重要な考慮要素とされる傾向にあります。
もっとも、15歳以上の場合と比べると、両親の離婚に際して不安や葛藤を抱え、真意をうまく伝えられないということもあります。
そのため、意思確認においては家庭裁判所調査官との面接などにより、態度や行動もあわせて観察され、その上でどのように考慮に入れるかについても検討されることが多いです。
まとめ
以上、親権をいつまで行使できるのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
親権は、子どもが成人に達するまで行使できます。
かつては、成人年齢は20歳でしたが、法改正により18歳に引き下げられました。
そのため、現在では、親権を行使できるのは、子どもが18歳に達するまでとなります。
子どもが18歳に達したら、子どもは自分自身で進路や住む場所を決められるようになり、自分の財産は自分で管理できるようになります。
また、一人で有効な契約をすることができるようにもなります。
もっとも、子どもが成人して親権に服さなくなっても、親子の関係がなくなることはありませんし、引き続き親による経済的・精神的な支えが必要になる場合は多いです。
親権がなくなることによる影響等をよく理解したうえで、必要な対応をしていくことが重要です。
当事務所には、離婚問題を専門的に扱う弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、親権問題にお困りの方を強力にサポートしています。
LINEなどによるオンライン相談にも対応しており、全国対応が可能です。
親権問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?



